未完成から始まる共創、“再生”を形にする実験の場「リジェラボ」
 YAMAHA MOTOR Regenerative Lab(通称:リジェラボ)
YAMAHA MOTOR Regenerative Lab(通称:リジェラボ)
共創スペース「リジェラボ」について、概要や立ち上げの経緯などを教えてください。
これからの時代に向けて、自然環境・コミュニティ・人間性の再生、つまり「リジェネラティブ(再生的)」につながるような事業の開発を考えたいとなったときに、自然環境というシステムは非常に大きいため、これは当然1社単独で実現することはできません。そこで、様々な知見やスキルをお持ちの方や企業さまと一緒に、コクリエーション(共創)していきたいと考え、開設したのが「リジェラボ」です。文字通り「リジェネラティブ」、つまり「再生」をキーワードに、自然環境や地域社会との共生も重視しながら、事業や活動を共創していく場です。
共創スペースをどのような空間にするかについて検討を重ねていたところ、「リジェネラティブという概念を、形で表してみてはどうだろうか」というアイデアが出て、そこからリジェネラティブを表現する場所を模索した空間づくりが始まりました。
当社は製造業ですので、私たちが製品として世に出したものは、使い終わると廃棄することになります。見方を変えると、最終的には捨ててしまうものを製造している、とも言えます。だからこそ、製造したものに、再び新しい命を与え、循環させることでリジェネラティブにしていけないか。そういった考えのもと、たとえば弊社製のプール槽を使ったデスクや、弊社のボートのハンドルを使ったテーブルなどを作成し、それらを共創スペース「リジェラボ」で活用しています。
 ヤマハ発動機製プール槽を使用したデスク
ヤマハ発動機製プール槽を使用したデスク
また、空間としてはあえて「未完成」、つまり「完成させない」ことを意識し、開設後も社内外の様々な方々と共創しながら、新たな要素を加えていく。そんな「変化し続ける未完成なオフィス」というコンセプトで設計・デザインしています。
さらに、自然環境の再生にも挑戦する企業として、都市部にありながら自然が感じられるスペースにしたいとの想いもありました。当社の本社がある静岡県に、社内公認クラブ「森マウンテンバイククラブ」のメンバーたちが有志でつくったマウンテンバイクのコース「ミリオンペタルバイクパーク」があるのですが、そのコース脇で拾ってきた木の実や枝をインテリアの素材に利用したりもしています。
 ミリオンペタルバイクパークにて採集した木の実や枝を樹脂で固めて成形したテーブル
ミリオンペタルバイクパークにて採集した木の実や枝を樹脂で固めて成形したテーブル
その結果、オフィスのあちこちから、設置している展示や物をきっかけに、「リジェネラティブってなんだろう?」といった会話が生まれています。「リジェネラティブという概念を、形で表してみてはどうだろうか」というアイデアが具体化し、そこからリジェネラティブについて考える機会が生まれていることを実感しており、大変うれしく思っています。
実体験を通して社員に根づくリジェネラティブの芽
「リジェネラティブ」という言葉がまだ一般的ではない中、「リジェラボ」のコンセプトは、貴社の中でどのように受け入れられていったのでしょうか?

当社はオートバイやボートなどのメーカーですが、そもそもそういうものが好きで入社する社員が多いんです。平日は職場でオートバイやボートを作っていますが、実は休日もそれを使って遊んだりしています。朝、波に乗ってから出社する、山を走ってから出社する、そういう社員も一定数います。
つまり、海や山、湖などによく触れているので、「豊かな自然の恩恵で、我々は遊べるし仕事もしているんだ」ということを、実体験として持っている社員が多く在籍しています。同時に、遊びの中で自然の中に身を置くことが多いからこそ、「山の雪が少なくなっている」「アマモ(海藻)がなくなってきた」など、自然環境が変化してきていることを肌感覚で感じる者が多いのだと思います。
当社は自然の恩恵で遊ぶという体験を提供しているのに、それができない自然になってきている。「だったら、それを再生させるために動くべきなんじゃないか」という考えは、コンセプトに関する議論の中で自然に湧き上がったものでした。
当社の業種は一般的に「輸送機器」として捉えられがちですが、製品ポートフォリオ全体で見ると、実はオートバイや電動アシスト自転車などアスファルトの道路を走る乗り物以外にも、山、林、海、湖、空がフィールドの製品も多くあります。そのため、「企業の責任としてCO₂を減らさないと!」という義務感ではなく、「自分たちのフィールドを守るため、自らそうしたい!」という自主的な想いが社員の魂の中に入っているように感じます。
「人・自然・コミュニティ」をつなぐヤマハの共創思想
「地球がよろこぶ、遊びをつくる」というキーメッセージには、どのような想いが込められているのでしょうか?
当社はオートバイメーカーとして創業し、一貫して小型エンジンをコア・コンピタンスとして横展開してきました。開発のベースにあるのは「こんな乗り物あったら面白いよね」という好奇心です。
言い換えると、乗り物というのはあくまでも「手段」であって、我々が作っているのは「遊び」なんだという想いがあるのです。自然をフィールドとして遊びを作ってきた企業として、これからは“地球”がよろこぶ遊びをつくっていこう、と考えています。
そういう想いや活動を紹介するウェブサイト「RePLAY!」も開設しました。ここでは活動の成果を公表するだけでなく、構想しているプロジェクトや、そこで直面している課題などもオープンにし、その課題を解決するために共創してくださる仲間も募集しています。これはリジェネラティブな社会の実現に向け、あらゆる方々に「一緒に取り組みませんか」といったメッセージの発信でもあります。
その結果、まだ活用されていないような森の資源「クロモジ」を使ってタンブラーやドリンクを作ってみたり、マイクロプラスチックを回収するための装置を考案してみたり、様々な企業さまやパートナーさまとの共創プロジェクトが生まれてきています。まだ事業レベルにまでは至っていませんが、こうした活動をさらに加速させたいと思っています。
 マイクロプラスチックを回収するビーチクリーン器具の試作機
マイクロプラスチックを回収するビーチクリーン器具の試作機
実際の活動で、大切にしている考えや流儀などはありますか?
ものづくりの会社だからなのかもしれませんが、当社には「三現主義」という考え方があります。デスク上だけですべてのことができる業態ではないこともあり、やはり「現場に行くことが大切」ということです。現場へ行けば、様々なことを五感で感じ、遊ぶイメージが具現化でき、インスピレーションを得られることもあります。
また、現場には、地域社会からも一目置かれるような「凄い人」が必ずいて、その人から現場の厳しさを含めて“本場”を学ぶことができます。その上で、安全性や品質をどう担保しながら「遊び」を普及させるか、それをどんなパートナーさんと解決していくのか……。
共創推進グループが新しい事業や活動を創造していく際には、「ゲンバヘ行く」「ホンバから学ぶ」「何度も実験する」姿勢を、流儀として大切にしています。
「地球がよろこぶ遊び」を、「人間性、コミュニティ、自然環境という3つの『再生』を実現する取り組み」と定義されていますね。
たとえば、今の日本で課題となっている環境問題のひとつが放置林です。自然環境は、一度人の手が介在したら、原則として手を入れ続けないと維持できません。開発の手を入れたものの、その後立ち行かなくなり放置されたことで、荒れ果てた山になってしまうことも多々あり、そうした地域では、害獣被害やがけ崩れなどの災害リスクが高まります。裏を返せば、人が介在し続けることによって、自然も維持・再生できるのです。
また、人間が都会だけで生きていくことは、難しいとも感じています。里山みたいなところに住むかどうかは別として、山や海でリフレッシュする時間も必要ですよね。自然の中に出かけて行けば、価値観を共有できるような仲間との出会いもあり、関係人口が増えることで地域コミュニティの再生にもつながっていく。人・自然・コミュニティ、この3つが上手く回っていくと、より良い世の中になるのではないでしょうか。
気づきを行動へ、“リジェネラティブ”を広げるための次なる一歩
「リジェラボ」を通じた活動の手ごたえは、いかがでしょうか?
特に「リジェネラティブ」や「ネイチャーポジティブ」という文脈で事業探索されている新規事業開発の方には、材料系から情報系まで業界に関係なく、多くの方に興味を持っていただいています。そういった側面では、「リジェラボ」のコンセプトが共感を生んでいることに手ごたえを感じています。
今後は、ある程度の規模感のある企業の方々が、どんどん仲間になってくれると嬉しいですね。そのためには、他人事、他社事ではなく、自分たちも参加できる、参加したい、と感じていただけることが重要だと感じています。
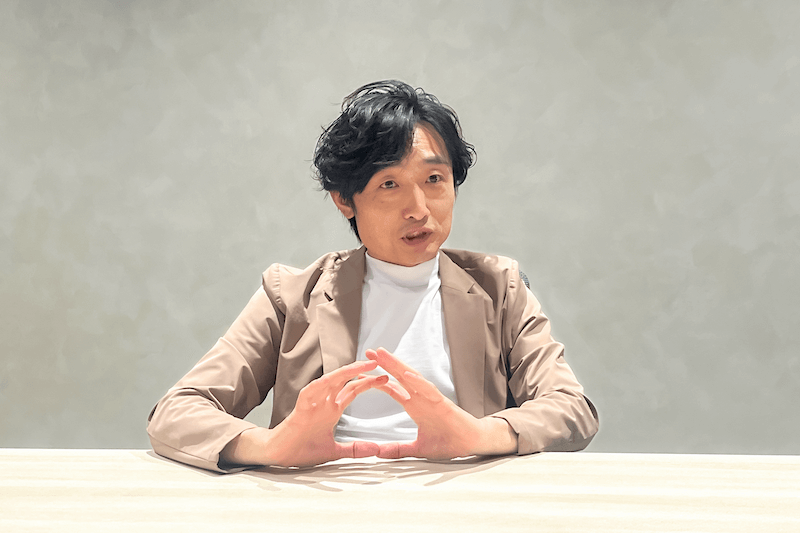
また、「地球がよろこぶ遊び」を創造していくことは、取り組みの継続性につながると考えています。CO₂排出量の削減など環境問題や社会課題の解決は、どうしても歯を食いしばって取り組むイメージになりがちですが、アクティブに無理なく続けていくためには、実は我慢より遊びの要素が必要なのではないでしょうか。
今後の展望について聞かせてください。
自然側から見ていく視点と、都市生活(人間側)から自然を見ていく視点、この2つの視点を統合することが課題であり目標です。たとえば、リジェラボの活動で気づきを得た人たちが、課題感を持って自然の中へ行く――この一連の流れを、パッケージ化していきたいと考えています。その実現に向けて企画を立てていますが、パッケージツアーなどは当社で企画や運営を行ったことがないので、新たなパートナーさんも必要です。防災関係やアウトドア・ブランドの方にもご興味を持っていただいています。彼らとも、コラボしながら何か創り出せるといいなと思っています。
そして、その前提として「リジェネラティブ」という言葉や概念そのものの認知を広げ、浸透させていく取り組みも進めていきたいと思っています。
リジェネラティブは、決して農業だけに関係することではなくて、実は身近な話で、かなり奥が深い。歯を食いしばらなくても、自分事としてできることがあることを、まずは伝えていきたいです。そして気づきを得た仲間たちと一緒に、リジェネレーションのムーブメントを創りたいですね。
取材時のダイジェスト版動画も提供しています。ぜひ、こちらからご視聴ください。
.png?width=680&height=356&name=PLAYERs%2308_%E5%8B%95%E7%94%BB%E3%82%B9%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%80%E3%83%BC%E7%94%A8(16_9).png) https://www.youtube.com/watch?v=WPba5czd76I
https://www.youtube.com/watch?v=WPba5czd76I








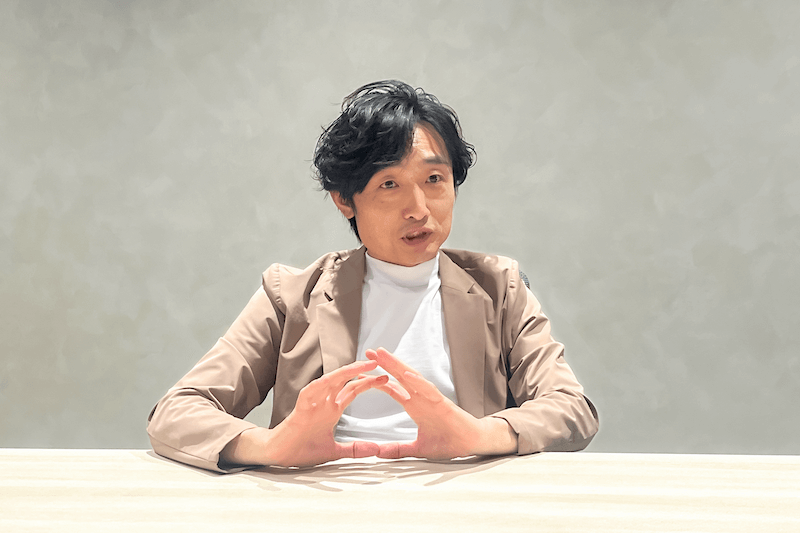
.png?width=680&height=356&name=PLAYERs%2308_%E5%8B%95%E7%94%BB%E3%82%B9%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%80%E3%83%BC%E7%94%A8(16_9).png)

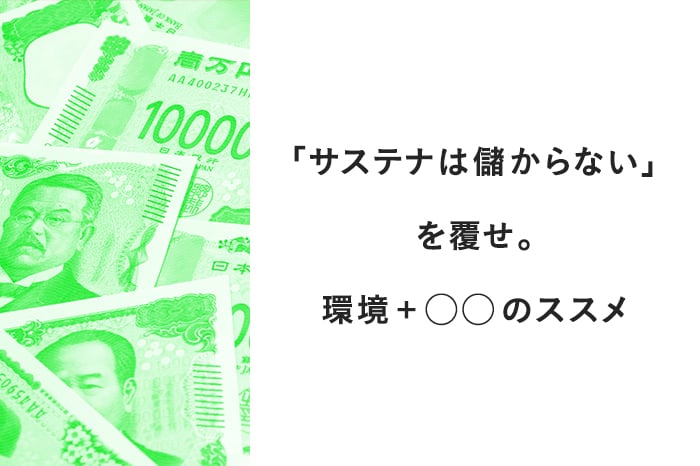











.png?width=600&name=%E3%83%97%E3%83%A9%E5%9B%B3%E9%91%91%E3%83%90%E3%83%8A%E3%83%BC_640260%20(002).png)