環境配慮と機能性や安全性のジレンマ。条件に合う素材を地道に探して出会った「Prasus®」
1918年の創業以来、魔法瓶を中心に人々の暮らしに寄り添う製品を届けてきた象印。近年では、「きょうを、だいじに。」というコーポレートスローガンを軸に、炊飯ジャーや電気ポットといった調理器具製品を提供する、生活に身近な存在だ。同社のボトルやケトルを使ったことがあるという人も多いだろう。
そんな象印は、現在のようにサステナビリティが叫ばれる以前から、環境への取り組みを独自に行なってきた企業でもある。例えば、2006年からマイボトル利用の推進を開始。外出先でマイボトルに給茶(有料)できる「給茶スポット」を全国に設置したり、社内の自動販売機からペットボトル製品をなくしたりと、環境負荷を減らすアクションを地道に続けてきた。
徳岡さん「環境への取り組みは以前から続けてきたので、社内でのハードルは高くありません。むしろ、それを実行することが良いことだという文化が根付いていると思います」
.jpg?width=2000&height=1332&name=zojirushi-2-1_2%20(1).jpg) 徳岡卓真さん
徳岡卓真さん
そんな中、象印では「炊飯ジャーでも何かできることはないか」と、環境に配慮した素材の検討を数年前から始めた。しかし、当時市場に出始めていたバイオマスプラスチックは、炊飯ジャーのように長期間使う製品に必要な耐久性を満たせなかった。さらに、リサイクル性にも課題があり、採用できる素材はなかなか見つからなかったという。
徳岡さん「当時主流だったのは、紙や竹の繊維などをプラスチックに混ぜ込んだもので、これらはリサイクルや強度の面で課題がありました。また、自然環境で分解されることを謳っているものもありましたが、炊飯ジャーのように長期間使う製品では、意図しない分解や劣化が起こる恐れがあります。食品に直接触れるものなので、これでは問題です」
三嶋さん「仮に機能的には問題がなくても、リサイクル後の用途が工事現場で使う三角コーンなどに限られてしまうなど、本質的に環境に良いと思える素材を見つけるのは、簡単ではありませんでした」
そんな中、素材の展示会で出会ったのが、プライムポリマーのマスバランス方式(※)によるバイオマスプラスチック「Prasus®」だった。
※製品を原料から加工・流通させる工程において、ある特性を持った原料とそうでない原料が混合される場合に、特性を持った原料の投入量に応じて、生産する製品の一部にその特性を割り当てる手法のこと。再生可能な資源であるバイオマス等の活用を促進させる効率的なアプローチとして注目されている。
性能はそのまま、移行コストもゼロ。メーカーの現実的な希望を叶える賢い素材
プライムポリマーは、主にPP(ポリプロピレン)やPE(ポリエチレン)を製造・販売する企業だ。「Prasus®」は、同社が展開している、新しいフィードストックを使用したマスバランス方式による環境配慮型PE/PPのブランドである。
その特徴は、バイオマス由来でありながら、石油由来品と全く物性が変わらないこと。そのため、従来の石油由来品と比較しGHG(温室効果ガス)排出量を大幅に削減できるだけでなく、既存の生産設備や製造プロセス、リサイクルプロセスをそのまま利用でき、製品の品質や耐久性、安全性などを損なうこともない。
三嶋さん「『Prasus®』は、私たちが要求するプラスチックとしての品質が、従来の石油由来の製品と全く変わりません。さらに、日本の食品衛生法にも適合しており、食品に触れる製品にも安心して使用できる。また、リサイクル時にも高い価値を保てることも、良いポイントでした」
.jpg?width=2000&height=1332&name=zojirushi-4-1_3%20(1).jpg)
三嶋一徳さん
さらに採用を後押ししたのが、素材の使用条件を変えずに、既存の製造プロセスをそのまま活用できる点だった。
徳岡さん「メーカーの視点から見ると、従来の石油由来品と全く同じように成形できる点は非常に重要です。新たな設備投資や、金型の調整、品質評価のやり直しといったプロセスが不要になるため、導入のハードルを大きく下げることができます」
冨永さん「徳岡さんがおっしゃった通り、新たな素材を使用する場合、通常はその素材を用いた成形評価や細かな条件変更、金型修正に加え、時には新たな設備投資が必要となります。しかし、『Prasus®』はこれらの条件を変えずにお客様の既存設備に投入できるため、移行コストと時間をかけずに切り替えられることが特徴です」
一方で、素材自体の価格は石油由来品より高くなるため、経済合理性とのバランスを取ることも必要だった。商品の外郭部品すべてに採用検討をしたこともあったが、部品単価が想定を大きく上回ることで断念。ただし、多くの商品に使いたいという想いもあり、炊飯ジャーの付属品である、しゃもじと計量カップに採用するという戦略を取った。
三嶋さん「炊飯ジャーの付属品は幅広い製品で共通して使われるため、いずれはより多くのお客さまに届けることを考えた上で、しゃもじと計量カップでの採用に至りました」
導入過程で唯一課題があったとすれば、「Prasus®」が採用するマスバランス方式というアプローチについて、社内の理解を得ることだったという。そこで2人は、プライムポリマーの担当者と密にコンタクトを取りながら、社内の各所に対して何度も粘り強く説明。その粘り強いコミュニケーションの結果、最終的には全社的にその価値を理解し、素材の採用を決めることができた。
どうせやるなら、100%で。「Prasus®」=環境に良い素材、と認知される社会に向けて」
象印の採用事例において特筆すべきもうひとつの点は、しゃもじと計量カップに使用されるプラスチックの全量を「Prasus®」に変更したということだ。
徳岡さん「やるからには、中途半端では良くないと考えました。コスト的には厳しい挑戦でしたが、思い切って100%での採用を決めました」
冨永さん「『Prasus®』は石油由来品よりも価格が高いため、マーケットの価格受容性を見極めながら、まずは製品に使用されるプラスチックの一部で『Prasus®』を採用されるのが一般的です。実際、マーケットの反応を見ながら、段階的に『Prasus®』の使用比率を上げていかれる企業様は多いです。その中で、最初から製品に使用されるプラスチックの全量で『Prasus®』を採用いただくことは、当社としても初めてのことでした」
.jpg?width=2000&height=1332&name=zojirushi-5-1_4%20(1).jpg)
「炎舞炊き」の炊飯ジャーと付属のしゃもじ、計量カップ
さらに象印は、自社のプレスリリースにおいて「Prasus®」の商標を明記。採用企業が「Prasus®」の商標を前面に出して発信するのはこれが初めてだ。この積極的な姿勢をプライムポリマーも歓迎している。
冨永さん「私たちは、『Prasus®』という素材が環境に配慮したものであることを、より多くのエンドユーザーの皆様に認識していただきたいと考えています。象印様のように『Prasus®』のロゴを使っていただくことは、ブランドの認知度向上につながり非常にありがたいことです。まさに、共に良い社会を作っていくためのパートナーシップを実現できたと感じています」
三嶋さん「こちらとしても、今後も見据えて『Prasus®』というブランドを活用させていただこうと考えました。『Prasus®=環境に良い素材』という認識が社会に広がっていけば、私たちの環境に対する取り組みも伝わりやすくなるはずです」
生活者との対話は、さりげなく地道に。“当たり前に”環境に良いことをしている会社でありたい
「Prasus®」の採用は、象印の社内にもポジティブな変化をもたらした。もともと環境への取り組みに積極的だった同社も、自社製品の素材転換に踏み込んだのは今回が初めてだったからだ。
徳岡さん「製品の『素材』として環境配慮型プラスチックを採用したことで、社内全体の関心も大きく広がったと感じています。営業部門をはじめ、全部署の社員が『Prasus®』やマスバランス方式について学ぶきっかけができ、環境問題への理解が深まりました」
.jpg?width=2000&height=1332&name=zojirushi-3-1_5%20(1).jpg)
取材が行われた「まほうびん記念館」。創業当時から販売してきた歴代の魔法瓶や炊飯ジャーなどが展示されている。
一方で、この変化を生活者にどう伝えていくのかと尋ねると、「さりげなく、象印らしく伝え続けていきたい」と三嶋さん。
三嶋さん「お客様にも、この素材を採用したことはきちんと伝えていく必要があると考えています。ただ、『私たちは環境のためにこんな活動をしています』と、大々的にアピールするつもりはありません。むしろ、お客様がふとした時に『そういえば象印の製品は環境に配慮した素材を使っている』と気づき、『環境配慮を当たり前にしている企業なんだ』と認識していただくのが理想です」
最後に、「Prasus®」をはじめとしたバイオマスプラや環境への取り組みを広げていくために読者に伝えたいことを聞いた。
徳岡さん「こうした環境配慮型の素材は、一社だけで採用してもコストはなかなか下がりません。しかし、多くのメーカーが採用するようになれば、量産効果でコストは下がり、もっと使いやすくなるはずです。
ですから、あらゆる業界の企業の方にもぜひこの流れに加わってほしい。そして、生活者の皆様にも、少しだけ素材を意識して製品を選んでいただくことで、この活動を後押ししていただけたら嬉しいです」
編集後記
今回の取材で象印が示したのは、「きょうを、だいじに。」というポリシーが製品開発だけでなく、「あした」の地球環境を大切にする姿勢にも深く結びついていることだ。例えば、質の良い代替素材を探しつつも、リサイクル性が低いものは採用しない。その徹底したスタンスからは、環境にとって何が本質的なのかを真摯に問い続ける姿勢がうかがえた。
また、素材転換と聞くと、多くの人が技術的なハードルを思い浮かべるだろう。しかし、その実現には、粘り強い社内コミュニケーションやコストを吸収する工夫といった、地道な企業努力も不可欠なのだ。今回の対談で垣間見えた象印とプライムポリマーとの強固な信頼関係は、まさにそのハードルを乗り越えるための原動力となっていたのだろう。
顧客への価値を損なうことなく、素材をバイオマスプラスチックに置き換えられる製品は、私たちが想像する以上に多く存在するのかもしれない。象印のように、身近な製品から確実な一歩を踏み出す企業が増えることが、バイオマスプラスチックが当たり前の選択肢となる社会を一日でも早く実現するカギとなるだろう。そうした企業の挑戦に、これからも注目していきたい。
取材時のダイジェスト版動画も提供しています。ぜひ、こちらからご視聴ください。

https://youtu.be/FrJdCPkH7pA
.png?width=2000&height=1333&name=PLAYERs%20%2310_%E4%BF%AE%E6%AD%A3%E7%89%88(3).png)
.jpg?width=1000&height=666&name=zojirushi-6_1%20(1).jpg)


.jpg?width=2000&height=1332&name=zojirushi-2-1_2%20(1).jpg)
.jpg?width=2000&height=1332&name=zojirushi-4-1_3%20(1).jpg)
.jpg?width=2000&height=1332&name=zojirushi-5-1_4%20(1).jpg)
.jpg?width=2000&height=1332&name=zojirushi-3-1_5%20(1).jpg)

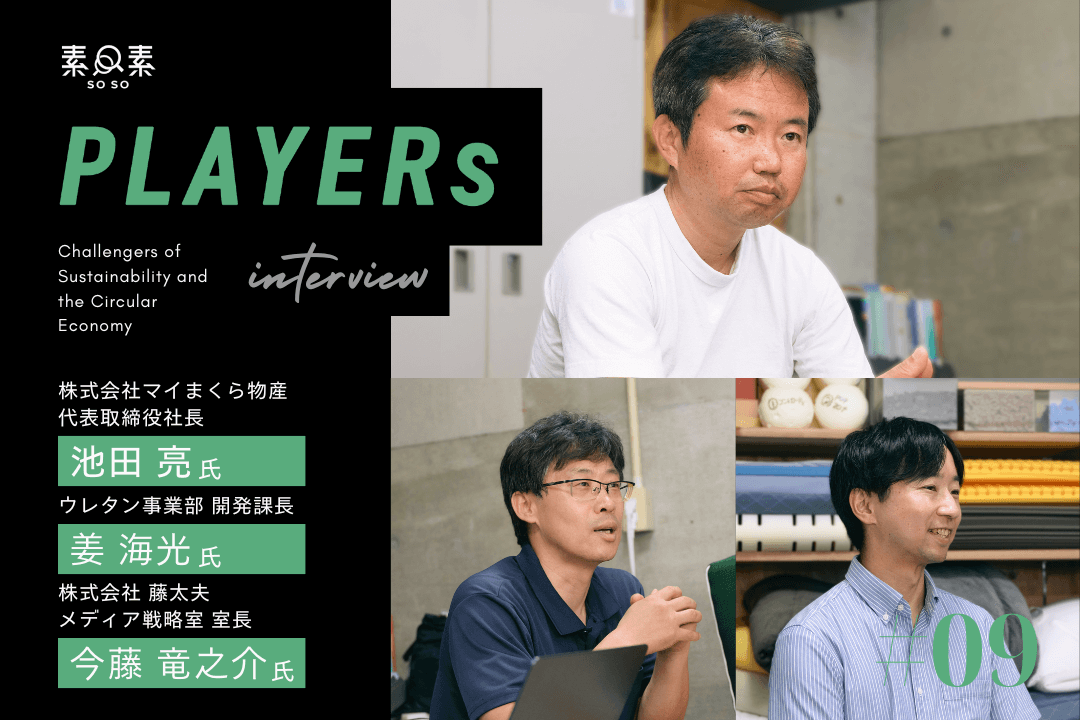
_%E5%89%8D%E5%8D%8A.png)




_%E8%A8%98%E4%BA%8B%E7%94%A8(1080%20_720).png?width=220&name=PLAYERs%2313(%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E3%82%B7%E3%82%B0%E3%83%9E)_%E8%A8%98%E4%BA%8B%E7%94%A8(1080%20_720).png)






.png?width=600&name=%E3%83%97%E3%83%A9%E5%9B%B3%E9%91%91%E3%83%90%E3%83%8A%E3%83%BC_640260%20(002).png)