- サステナブルな未来
- サーキュラーエコノミー
- カーボンニュートラル
「サステナは儲からない」を覆せ。環境+◯◯のススメ

|
「環境にやさしい」だけでは、商品は売れない。 これは環境問題に取り組むビジネスパーソンにとって、目を背けられない不都合な真実だ。 調査によると「環境問題を意識して取り組むことは当たり前」と答える人が45.2%いる一方で、「環境問題を意識した行動をしている」と答える人は21.3%(注1)。環境意識が高い層でも、環境に配慮した行動をとるとは限らないのだ。 これは今後、普及が望まれる環境配慮製品についても同様だ。消費者の意識だけではなく、行動まで変えるためには、新たな事業創出、製品開発のあり方や、メッセージの伝え方が求められる。 では具体的にどう行動すべきなのか。生物由来のバイオマスプラスチックやリサイクル等プラスチックの環境配慮製品の市場浸透を目指す三井化学グリーンケミカル事業推進室の三國達也氏が、サステナブルマーケティングを専門とする早稲田大学ビジネススクール教授の川上智子氏に話を聞き、その道筋を話し合った。 (注1)三井化学が2025年に1,000人の消費者に対して実施した、消費者の環境意識理解調査。 |
売るために必要なのは「環境+◯◯」
三國 三井化学では、素材メーカーの立場から環境配慮製品の市場創造に取り組んでいます。
具体的には、植物由来のバイオマス原料から作られるバイオマスプラスチックへの転換を推進するソリューションと、廃プラスチックを資源と捉えて有効利用するリサイクルソリューションの提供を進めています。

バイオマスプラスチックやケミカルリサイクル材の最大の強みは、従来の石油由来のプラスチックと全く同じ品質を保ちながらも、CO2排出量を減らせること。
一方でやはり製造コストは上がってしまう。そういった背景から、日本の市場への浸透にはまだ課題を感じているのが正直なところです。
川上先生は、環境貢献と経済利益の両立を実現させるためのマーケティング論がご専門ですが、環境配慮製品の受容度という観点で、日本市場をどう見ていますか。
川上 日本市場の環境意識は、欧州などと比べれば低い傾向にあると思います。
現に今年4月に発表された「人類と気候変動レポート2025」(注2)の結果は、「日本人の気候変動対策への意識は32カ国中最下位」とセンセーショナルに報道されましたね。

その一方で、日本のペットボトル回収率は9割を超え、欧州の約6割、米国の約3割と比べても、高い水準を維持しているといった側面もあります(注3)。
日本人の環境意識が低いとは一概に言えず、消費者行動はセグメントによって異なりますし、適切なコミュニケーションによって意識や行動は大きく変わり得るものだと考えています。
(注2)「人類と気候変動レポート2025」世論調査会社イプソスが32か国の2万3745人を対象に実施した調査。
(注3)日本:PETボトルリサイクル推進協議会、欧州:Wood Mackenzie社、米国:NAPCOR(National Association for PET Container Resources) 日本と欧州は2020年の数値、米国は2019年の数値。
三國 私たちも今年、日本の消費者の環境に対する意識調査を行い、ホワイトペーパーをまとめたんです。
「日本の消費者の環境意識は海外と比較して低い。だから環境配慮製品は売れない」という認識が浸透している中で、実際にどの程度の需要、ポテンシャルがあるのか、定量的に把握したいと考えたからです。
調査から得られた一つ目の示唆は、価格が高くても環境配慮製品を選ぶ層が一定存在していること。調査ではその層を「エコバリュー派」と定義したのですが、彼らは市場全体の約25%を占めています。
また、この「エコバリュー派」の多くが価格アップに対してある程度許容することもわかりました。商材により具体的な金額は異なりますが、シャンプーのような日用品であれば、3人に1人が15-30%程度高くても購入したいと回答しました。
価格を重視する「コスト派」が多数派ではあるものの、市場全体の4人に1人は価格のハードルを乗り越えて環境配慮製品を選択する意向を示したことは、重要な示唆ではないかと考えています。

二つ目の示唆は、エコバリュー派は「環境にやさしい」という要素に加え、別の価値が付与されれば、価格の受容性がさらに高まるという結果です。
たとえば、従来品に対して環境にやさしい素材を使用しているだけの場合と、そこに加えてシャンプーの詰め替えやすさといった利便性や、クルマの場合は自動車保険の割引適用といった経済的メリットが提供されるケースでは、価格上昇を許容できる割合が高まったのです。

環境対応は組織体制から見直そう
川上 非常に面白いですね。こうした調査結果を見ると、「環境にやさしいことをどう打ち出すか」だけではなく、「どのような付加価値をつけて作るか」という設計や開発段階の工夫も求められることがわかります。
三國 ええ。調査結果を踏まえて考えていたのは、こうした「付加価値のある環境配慮製品」をつくるためには、組織体制から変えていく必要があるのではないか、という観点です。
というのも多くの日本企業では、例えばサステナビリティ推進室のような環境推進を担うコーポレート部門と、売上責任を担う事業部門やマーケティング、購買、品質保証等の部門が分かれているケースが多いですよね。
これでは、環境対応と製品開発の観点がうまく噛み合わないのでは、と。

川上 ええ、おっしゃる通りです。現状多くの企業が環境というテーマをIRや広報の課題と位置づけ、本社のコーポレート部門による対応にとどまっていますよね。
ですがそれでは、環境対応が広報・IR用の「見せるための施策」にとどまり、現場や事業部門での実効性ある取り組みに広がりづらい。
本来は、環境対応は本業でこそ取り組むべきです。顧客の行動変容をいかに起こせるかというマーケティング視点を持ち、事業部門とコーポレート部門が一蓮托生で進めていく必要があるのです。
三國 確かに我々が企業に実施したアンケートでも、サステナビリティ推進室などの管理部門が戦略を策定しても、事業部門がなかなか実行してくれない、あるいは組織が縦割りで、部門間の議論や連携が進まないといった課題が目立ちました。
このような課題は現状、「既存製品のCO2をいかに減らすか」といった既存の枠組みの中での議論が中心となっている印象です。

ですが調査結果からも示唆されるように、サステナビリティへの対応は「イノベーション創出の機会」と捉えるべき。
その観点に立った時、企業がサステナビリティの視点でイノベーションを推進していく上で、具体的に組織をどのように変えていくべきでしょうか。
川上 一番有効な方法は、サステナビリティ推進部門に、各事業部で成果を上げた人材をアサインすることだと考えています。
そうすれば、本社のサステナ部門と事業部門の信頼も築きやすいし、実行力を伴った本業側の施策を進めやすくなります。こうした人材配置を経て、本業での環境貢献の成果を上げている例を私も複数みてきました。

総じて重要なのは、組織がアンラーンする能力ですよね。
環境対応に本気で取り組むためには、これまで蓄積してきたビジネスモデルや組織体制を一度見直し、再構築する必要がある。
その際には、これまでのやり方を一度捨てられるか、いかにアンラーンできるかが、鍵を握るのです。
発信で大事なのは手触り感
三國 一方で、実際に製品を売る段階でどのようにコミュニケーションすべきか苦慮している企業が多いのも実情です。
環境配慮製品を消費者に受け入れてもらうために、川上先生はどのようなコミュニケーションが有用だとお考えですか。
川上 消費者に買ってもらうための最後の一押しは、やはりクリエイティブの力ですよね。
正直今は、どの会社も「真面目にやり過ぎ」だと感じています。「我が社はこんなに環境に配慮しています」と打ち出しても、他社との差別化にもならないし、消費者にも刺さらないですよね。
ですがそのクリエイティブこそが難しい。というときに有用なのが「SHIFT」と呼ばれるフレームワークなのですが、これは消費者や個人の“わかっているのにできない”という行動変容の壁を乗り越えるために作られたものです。

その中でもTangibility(具体性)は重要だと感じています。
たとえば「地球の未来のために行動しましょう」といった抽象的なメッセージでは変えられない行動も、「あなたの行動が◯◯本の木を植えることにつながりました」という具体的な貢献が見えれば、一気にモチベーションが高まります。
この手触り感が大事なんですよね。
三國 非常に参考になります。我々もバイオマスプラスチックの打ち出し方は常に模索しているのですが、「生物由来」「プロダクトのCO2削減に効果的」などの価値を、より手触り感を持って伝えるコミュニケーションを考案していかなければいけないですね。
川上 そうですよね。これはさすがに言い過ぎかもしれませんが、たとえば三井化学が取り組んでいるケミカルリサイクルについても、「何度でも再生産・再利用できる」という特性を全面的に打ち出し、「無限ループのプラスチック」といった言葉でブランディングするのはいいかもしれません。
伝え方によっても、バイオマスプラスチックやリサイクルの受け止められ方は大きく変わると思います。

環境対応は制約ではなく、新しい価値創造の機会。そんな発想の転換から、日本発の革新的な製品やサービスが生まれてくることを期待しています。
|
三井化学のBePLAYER/RePLAYERの取り組み: |
|
<公開資料:「環境か、コストか。私達の最適解は」>
|
執筆:塚田有香
撮影:小池大介
デザイン:吉山理沙
編集:金井明日香
NewsPicks Brand Designにて取材・掲載されたものを当社で許諾を得て公開しております。
2025-07-18 NewsPicks Brand Design



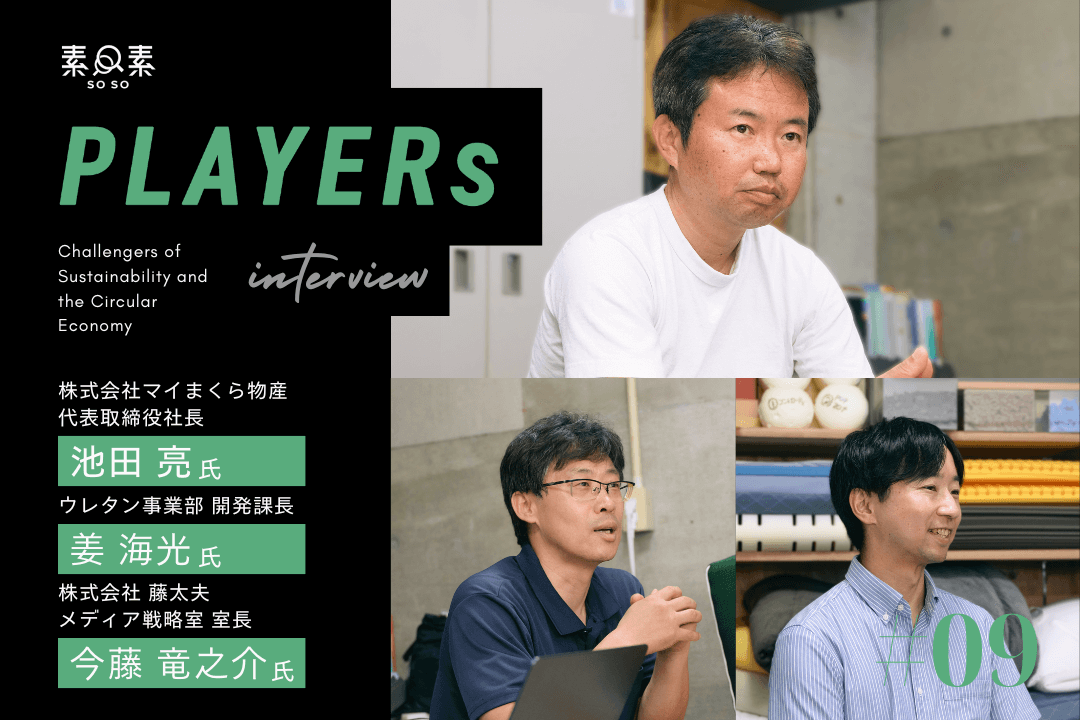




_%E8%A8%98%E4%BA%8B%E7%94%A8(1080%20_720).png?width=220&name=PLAYERs%2313(%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E3%82%B7%E3%82%B0%E3%83%9E)_%E8%A8%98%E4%BA%8B%E7%94%A8(1080%20_720).png)






.png?width=600&name=%E3%83%97%E3%83%A9%E5%9B%B3%E9%91%91%E3%83%90%E3%83%8A%E3%83%BC_640260%20(002).png)