- サステナブルな未来
- カーボンニュートラル
地球温暖化とは?原因や仕組み、現状をわかりやすく解説

世界共通の社会課題の一つである地球温暖化。海面上昇や生物多様性の損失を引き起こす要因にもなっており、自然環境や人々の暮らしにさまざまな影響を及ぼしています。二酸化炭素をはじめとした温室効果ガスが、地球温暖化にどのように影響しているのか、その原因や仕組みなどをわかりやすく解説します。
地球温暖化とは?そのメカニズムや温室効果ガスについてわかりやすく解説
地球温暖化のメカニズムと現状
地球温暖化とは、大気中に放出された二酸化炭素(CO₂)など温室効果ガスの濃度が高まることで、地球の平均気温が上昇することを指します。
世界気象機関(WMO)によると、世界の年平均気温は、様々な変動を繰り返しながら上昇しており、特に1990年代半ば以降は上昇幅が拡大。2024年の世界平均気温は観測史上で最高値を更新し、産業革命前と比べた上昇幅は1.55℃に達しました。

地球温暖化の原因となる温室効果ガスとは?
地球温暖化の原因となる温室効果ガス。最も排出量が多いのは二酸化炭素(CO₂)ですが、メタン(CH4)や一酸化二窒素(N₂O)、代替フロン等4ガスなども温室効果ガスです。この温室効果ガスには、地球の自然環境や生物にとって不可欠な役割があります。
地球の表面は、太陽から降り注いだエネルギーによって暖められます。その熱は赤外線のエネルギーとして放出されます。しかし、大気中の温室効果ガスがあることで赤外線のエネルギーの一部が留まり、地球の表面が温められ、地球の平均気温は約14℃という生物の生存が可能な環境に保たれています。もしも大気中に温室効果ガスがなかったら、その熱はそのまま宇宙空間に放出されてしまい、地球の平均気温はマイナス19℃になると言われています。
地球温暖化の仕組みや歴史的な背景
地球を生物の生存が可能な環境に保つ上で大切な役割を果たしてきた温室効果ガス。その一つであるCO₂は大気中に放出されると主に植物や海洋に吸収され、残りが大気中に留まります。
CO₂を構成する炭素はさまざまな形で動物の身体や岩石、土壌に蓄積されています。そして、動物や植物、魚、プランクトンなどが寿命を迎えると微生物によってCO₂や水、窒素などに分解されます。このように、炭素は形を変えながら陸地と海洋、大気を循環しており、産業革命以前の地球では大気に放出されるCO₂と、大気中から植物や海洋などに取り込まれるCO₂の量がほぼ均衡を保ってきました。
しかし、18世紀後半に産業革命が起こり、石炭や石油など地中に埋没している化石資源が大量に消費されるようになりました。すると、森林や海洋でのCO₂が吸収量を工業化によるCO₂排出量が上回るようになり、大気中のCO₂濃度が高くなっていったのです。
世界気象機関(WMO)の温室効果ガス年報によると、大気中のCO₂濃度は産業革命以前(1750年以前)の約278ppmに対し、2023年には約420ppmと51%増加しています。CO₂の他にも、メタン(CH4)や一酸化二窒素(N₂O)といった温室効果ガスが増加していることもわかっています。
大気中の温室効果ガス濃度が高くなりすぎると、地表から放出される熱が宇宙空間に放出されずに地表に留まります。すると、地球の平均気温が上昇するというわけです。このように、産業革命以降の人間の活動が温室効果ガスの濃度を高め、地球温暖化が進行してきました。
<大気中の二酸化炭素の世界平均濃度>
出典:気象庁ホームページ「大気中の二酸化炭素濃度の経年変化」
地球温暖化-世界各地で起こる深刻な影響

人間の活動によって加速している地球温暖化。工業化の進展に伴い、温室効果ガスの排出量が増加する中で、大気中のCO₂の濃度は200万年のうちで最も高くなり、世界の平均気温も過去2000年の間には見られなかったスピードで上昇し続けています。
こうした地球温暖化の影響は以下のように多方面に及んでいます。
極端現象(異常気象)の増加
地球温暖化が進むと極端現象(異常気象)が多くなります。例えば、猛暑や豪雨、干ばつといった極端な気象現象が頻発し、私たちの生活やインフラにも大きな影響を与えるようになります。
生態系への影響
地球温暖化をはじめとした気候変動は、陸上と淡水に生息する動物や植物などの生物種の大部分について、絶滅のリスクが増えると予測されています。WWF(世界自然保護基金)によると、地球温暖化(気候変動)の影響を受けていると考えられている絶滅危機種は、2000年の約10種に対し、2024年7月時点で7040種にまで増加しており、生態系のバランスにも影響を及ぼしています。
海面上昇
地球温暖化の影響を受け、陸上の氷河や氷床に貯蔵されていた氷が融解して海に流れ込んでいることに加え、水温の上昇で海水の体積が膨張し、海面が上昇しています。これに伴い、海抜が低い地域や島国では洪水や浸水のリスクが高まり、そこに住む人々が移住を迫られる可能性があります。なお、気候変動に関する政府間パネル(IPCC)によると、世界の平均海面は1901〜2018年の間に0.20m上昇し、海面水位の上昇率は年々高まっています。1901年~1971年の間は1年あたり1.3mmの上昇でしたが、1971年~2006年には1年あたり1.9mm、2006年~2018年には1年あたり3.7mmの上昇となっています。
食糧生産への影響
気温の上昇や異常気象は、農作物にも悪影響を与えます。特に、干ばつや洪水が続くことで、作物の収穫量が減り、品質も悪くなることが心配されます。このため、地球温暖化に歯止めをかけなければ、世界各地で食糧価格の上昇や、食料不足が深刻化に直面する可能性があります。
このように地球温暖化が環境面にさまざまな影響を与えていることが明らかになった今、全世界で地球温暖化の対策が求められています。中でも重要なのが、CO₂をはじめとした温室効果ガスの排出量を抑えることです。そこで日本でも2020年10月に菅義偉内閣総理大臣(当時)が所信表明演説で「2050年までにカーボンニュートラルを目指す」ことを宣言しました。
地球温暖化の影響を軽減し、持続可能な未来を築くためには、温室効果ガス排出量削減に向けた取り組みをさらに加速させることが重要になっています。
※地球温暖化の影響については、「地球温暖化の影響とは?予測される未来をわかりやすく解説」にて詳しく解説しています。

https://www.youtube.com/watch?v=nq8G6Cg9TOg
|
三井化学では、「世界を素(もと)から変えていく」というスローガンのもと、 <「BePLAYER®」「RePLAYER®」>https://jp.mitsuichemicals.com/jp/sustainability/beplayer-replayer/index.htm |
- 参考資料
- *1:国際連合広報センター「2024年は史上最も暑い年に ― 国連の気象機関が発表(UN News 記事・日本語訳)」:
https://www.unic.or.jp/news_press/features_backgrounders/51488/ - *2:WORLD METEOROLOGICAL ORGANIZATION「2024年は気温上昇が一時的に1.5℃に達し、史上最も暑い年になると見込まれている。」:
https://wmo.int/news/media-centre/2024-track-be-hottest-year-record-warming-temporarily-hits-15degc - *3:WORLD METEOROLOGICAL ORGANIZATION(気象庁訳)「WMO 温室効果ガス年報」:
https://www.data.jma.go.jp/env/info/wdcgg/GHG_Bulletin-20_j.pdf - *4:環境省「温室効果ガスのメカニズム」:
https://www.env.go.jp/earth/ondanka/stop2008/06-07.pdf - *5:IPCC「IPCC AR6 WG1 SPM 暫定訳 政策決定者向け要約」:
https://www.data.jma.go.jp/cpdinfo/ipcc/ar6/IPCC_AR6_WGI_SPM_JP.pdf - *6:気象庁「大気中二酸化炭素濃度の経年変化」:
https://www.data.jma.go.jp/ghg/kanshi/ghgp/co2_trend.html - *7:環境省「2022年度の我が国の温室効果ガス排出・吸収量について」:
https://www.env.go.jp/content/000216325.pdf - *8:全国地球温暖化防止活動推進センター デコ活ジャパン「温暖化とは?地球温暖化の原因と予想」:
https://www.jccca.org/global-warming/knowleadge01


.jpg)
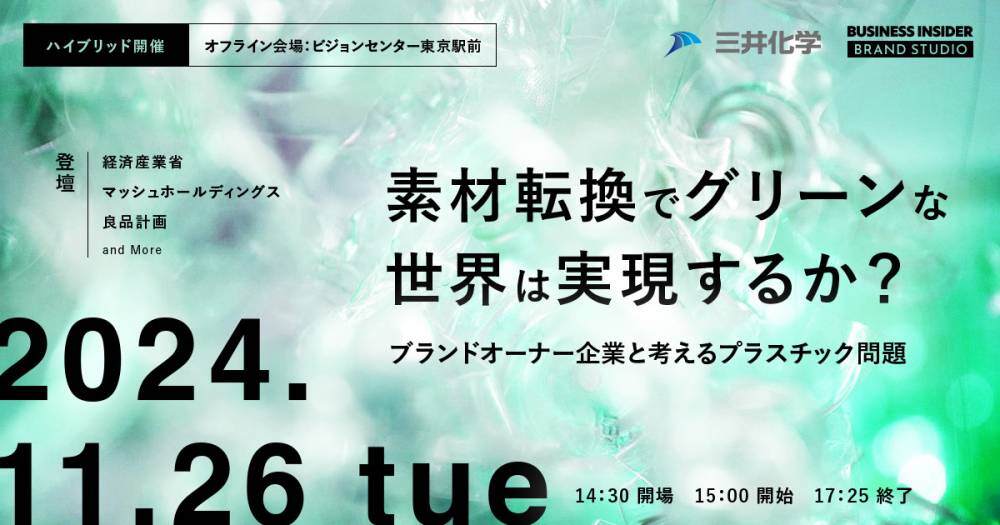











.png?width=600&name=%E3%83%97%E3%83%A9%E5%9B%B3%E9%91%91%E3%83%90%E3%83%8A%E3%83%BC_640260%20(002).png)