- サーキュラーエコノミー
- プラスチック
前編:EU循環経済政策の全体像と関連法規制を理解するためのポイント
_%E5%89%8D%E5%8D%8A.png?width=2000&height=1333&name=EU%E5%BE%AA%E7%92%B0%E7%B5%8C%E6%B8%88%E3%81%AE%E9%96%A2%E9%80%A3%E8%A6%8F%E5%88%B6(IGES%20%E8%BE%B0%E9%87%8E%E6%A7%98)_%E5%89%8D%E5%8D%8A.png)
近年、EUでは循環経済の実現に向け、環境面においても様々な法規制が導入されており、この分野における世界のルールメーカーとしての存在感を高めています。世界的な循環経済政策・関連法規制のトレンドを把握し、今後、ビジネスで求められる対応を的確に進めるべく、各国の企業がEUの規制動向に注目しています。
ただし、EUの循環経済・関連法規制の内容は膨大で、それぞれが複雑に関連し合うため、全体像を正確に把握するのは容易ではありません。そこで、その背景や読み解き方を、地球環境戦略研究機関(IGES)のプログラムコーディネーターである辰野美和さんに解説していただきました。
|
プロフィール 辰野 美和(たつの みわ) |
EU循環経済政策のベース「欧州グリーンディール」とその狙い
EUのさまざまな循環経済政策および関連する環境法規制を理解するうえでは、その柱となる戦略や、EUが直面する経済・社会状況や課題を把握することが第一歩となります。
近年、EUが次々と策定する様々な循環経済政策・法規制のベースにあるのが、2019年に発表されたEUの成長戦略「欧州グリーンディール」です。1930年代にアメリカのフランクリン・ルーズベルト大統領が世界恐慌で疲弊したアメリカの経済・社会を復興させるべく打ち出したニューディール政策になぞらえて、このような名称がつけられました。

欧州グリーンディールは、サステナビリティを中核に据えた、社会・経済を変革するための社会契約(Deal)であり、その目標は大きく2つあります。
1つは、2050年カーボンニュートラルの達成です。この目標は2021年に成立した「欧州気候法」に基づき、EU全体として達成することを法的に義務付けられています。この法律により加盟国に課された義務を履行しない国に対しては、行政・司法手段がとられる可能性があります。
もう1つの目標は、経済競争力の強化です。現在27カ国あるEU加盟国の中には、ドイツのように経済が比較的盤石な国がある一方、ワーキングプアの割合や失業率が高い国も少なくありません。EUでは、世界のGDPにおける割合が1990年代に比べ低下するなど、10~20年の長期スパンにおいて国際的な産業競争力の低下がみられ、過去複数回にわたる産業戦略も十分な成果をあげられていません。
そこで、この状況を打破すべく、「環境」と「経済成長」を両立させる成長戦略として掲げられたのが「欧州グリーンディール」です。
欧州グリーンディールの背景:エネルギー・資源の自給力強化
循環経済・サステナビリティをツールとして「環境」と「経済成長」を達成しようとする背景のひとつに、EUが抱えるエネルギー・資源の対外依存という大きな課題があります。
EUは長年、原油や天然ガスを主にロシアに大きく依存してきましたが、2022年のウクライナ侵攻をきっかけにエネルギー供給の脆弱性が浮き彫りとなり、経済活動にも深刻な影響を及ぼしました。このことは、EUが化石燃料の利用から低炭素化にシフトし、再生可能エネルギーや資源循環の推進によって、域内でのエネルギー・資源供給の自律性を高める方針をさらに加速させる契機となりました。
また、EUでは、「GX(グリーン・トランスフォーメーション)」と「DX(デジタル・トランスフォーメーション)」を「双子の移行(twin transitions)」と呼び、欧州グリーンディールや産業戦略の柱に据えています。
しかし、これらの移行は、例えばバッテリー、太陽光パネル、ICT機器などへの需要を喚起し、同時にこれらの製造に不可欠なレア・アースなど金属鉱物資源の需要も急激に増すことが予想されています。金属鉱物資源の多くは中国が供給しており、EUも中国に大きく依存しています。
こうした対外依存から極力脱し、資源確保を安定化させ、より自律した経済圏を構築することで、経済安全保障の強化およびグローバル市場での産業競争力を高めたいとする意図があります。
このように、欧州グリーンディールは、環境保護的な面だけではなく、EUの国際競争力強化を戦略的に組み込んだ政策となっています。

循環経済の実現に向けた7つの重点分野
欧州グリーンディールでは、サステナビリティは「カーボンニュートラル」と「経済成長」を同時に成し遂げるツールであり、そのためにあらゆる経済活動に“サステナビリティ”をインストールすることを宣言しています。
この欧州グリーンディールを具体的なプランに落とし込んだものが、2020年3月に発表された「新循環経済行動計画」です。いきなりすべての産業でアクションを起こすのは難しいため、エネルギー集約型かつ潜在的に循環性が高い「電気・電子・情報通信」、「バッテリー・自動車」、「容器包装」、「プラスチック」、「繊維」、「建設と建物」、「食品・水」などが重点産業と位置付けられています。
これらの分野を中心に法整備が進められており、例えば、バッテリー・自動車においては「バッテリー規則」「ELV規則(案)」、容器包装においては「PPWR(包装・包装廃棄物規則)」などの規制が策定されています。中でもプラスチックは汎用性が高い材料であるため、プラスチックに関する規制は様々な産業分野にも影響を与えることになります。
なお、ほぼすべての製品群を対象とする規則として、2024年に施行されたのがエコデザイン規則(ESPR)です。エコデザイン規則では、EU域内で流通する製品に対し、持続可能性に関する要件などを定めており、サプライチェーンにおける情報開示の仕組みのひとつとしてデジタルプロダクトパスポート(DPP)が導入されました。
他にも欧州グリーンディールの目標を達成すべく、様々なルールの立法プロセスが進行しています。
<EU環境法規制の背景と7つの分野>
参考:辰野様への取材記録を基に図式化
EUの循環経済政策・関連法規制を理解するうえで押さえておくとよいポイント
特にこれからEU規制の内容を把握しようとする方々にとって、頭に入れておくと良い点を解説します。
1. EUにおける資源利用・廃棄物管理の優先順位「廃棄物ヒエラルキー」
EUの循環経済政策および関連法規制を見ていく際、把握しておくと良いのが、まず「廃棄物ヒエラルキー(Waste hierarchy)」です。これは2008年に改正された「廃棄物枠組み指令」で提示されたもので、資源の利用や廃棄物管理の手段における優先順位を示しており、循環経済関連の法規制においても、このヒエラルキーに則って内容が定められていることが多々あります。
廃棄物ヒエラルキーで最も上位に位置付けられているのは、廃棄物を出さないような設計や使用抑制を行う「排出抑制(PREVENTION)」です。その次が「再利用のための準備(PREPARING FOR RE-USE)」、3番目が「リサイクル(RECYCLING)」、4番目が「回収(RECOVERY、例:熱回収)」、そして最後が「処分(DISPOSAL、例:埋め立て」です。
<廃棄物ヒエラルキー>
出典:European Commission「Waste Framework Directive」
このヒエラルキーを頭に入れておくと、様々な産業分野の規制において、なぜこのような要件が定められているのかという点が、理解・整理しやすくなるかと思います。例えば、先ほど触れたエコデザイン規則や後編で説明するPPWRにおける設計要件などは、「排出抑制」を実現するためのルールと捉えることができます。
2. EU法の階層
また、EUの法律を読む際、EUの法律体系が大きく3段階に整理できることを念頭に置くと、内容の構成が把握しやすくなります。
最上位には、EUの憲法的性格をもつEUの条約。
その次にあるのが、欧州委員会の提案に基づき欧州議会・理事会が共同で制定する法律で、「規則(Regulation:加盟国すべてに直接適用され、拘束力をもつ)」、「指令(Directive:各加盟国に国内法整備を義務付ける)」、「決定(Decision:特定の主体に拘束力をもつ)」などの形式をとり、循環経済・環境分野においてはこれらの法律によって、重要な法的要件が定められます。
その下に、詳細な定義や手続きなどを定める補足的な法律として、「委任規則(Delegated acts)」や、更に細かい事務手続きなどを示す「実施規則(Implementing acts)」などがあり、循環経済・環境分野においては、多くの場合欧州委員会が委任され策定します。
後編で解説するPPWR(包装・包装廃棄物規則)においても、軸となる内容は規則(Regulation)で述べられていますが、それに関連する細かな点は委任規則や実施規則で定めることが条文に記されています。例えば、PPWRでは、包装のリサイクル性能に関する等級付けが定められていますが、これらのより詳細な評価基準は、委任規則により2028年1月1日までに策定されることになっています。
欧州グリーンディールを実現するための資金「NextGenerationEU」

2050年カーボンニュートラルの達成や経済成長を目指す欧州グリーンディール。この成長戦略を実現するには膨大な資金が必要です。より確実な実行に向け、EUが財政面でどのような仕組みを構築しているかについて触れておきます。
EUは、資金調達のスキームに民間資本を政策実施へ導く手法を取り入れています。新型コロナによる経済的ダメージに対処するため、EUはいくつかの復興基金を創設しました。その柱のひとつが、「NextGenerationEU(次世代EU)」という約7500億ユーロの資金プログラムです。
この時期に、世界的にグリーン・リカバリーの動きが広がりましたが、EUでもこの復興計画の中心に欧州グリーンディールを据え、「双子の移行」に重点を置く方針が示されました。その名称からも分かるように、この資金プログラムは、次世代に向けた経済・社会の構造改革のためという位置づけです。
NextGenerationEUの大きな特徴は、EUを主体として債券を発行し(EU共同債)、本格的に市場から直接資金を調達するという点です。また、調達した資金をEUが加盟国に供与する際、加盟国が提出する復興計画には37%以上をグリーン移行、20%以上をデジタル移行に充当することが課されており、その使途が比較的明確にされています。この調達方法においては、債券購入者である企業や投資家などにとって、欧州グリーンディールなどの政策が適切に実施され、EU当局の財務状況が将来にわたり健全であるという信頼が必須になります。
現在のところ、投資家からの需要も高く、順調に資金調達が進んでいるという見方が主流です。税金や拠出金などによる公共事業への投資は、時に市場や市民の感覚から離れることがありますが、NextGenerationEUは、市場を介した資金調達方法であること、また調達資金の使途に比較的透明性があるため、政策を進める側と市場の感覚との乖離を防ぐ機能が働くという点で、画期的な手法となっています。
ここまでお話ししたのは、EUの循環経済の実現を目指す戦略「欧州グリーンディール」、関連法規制を理解するうえで押さえておくとよいポイント、政策実現のための資金調達方法など、EUの循環経済の全体像を把握するための内容です。
後編では、2025年に発効したPPWR(包装・包装廃棄物規則)やPFASに関する規制など具体的な法令の内容を解説し、日本企業に求められる対応についても触れていきます。
※後編:「PPWR」包装の持続可能性要件やEU規制に関して日本企業に求められる対応
※記事の内容はインタビュー対象者の見解に基づくものであり、IGESの見解を述べたものではありません。
|
三井化学では、「世界を素(もと)から変えていく」というスローガンのもと、 <「BePLAYER®」「RePLAYER®」>https://jp.mitsuichemicals.com/jp/sustainability/beplayer-replayer/index.htm |
- 参考資料
- *1:European Commission:
https://climate.ec.europa.eu/eu-action/european-climate-law_en?utm_source=chatgpt.com - *2:European Parliament “Enforcing EU climate legislation”:
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_BRI%282024%29762378?utm_source=chatgpt.com - *3: European Commission, “NextGenerationEU Green Bonds”:
https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/eu-budget/eu-borrower-investor-relations/nextgenerationeu-green-bonds_en?utm_source=chatgpt.com - *4:European Commission:
https://commission.europa.eu/business-economy-euro/economic-recovery/recovery-and-resilience-facility_en?utm_source=chatgpt.com - *5:蓮見雄・高屋定美「欧州グリーンディールとEU経済の復興」:
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jjce/62/2/62_2_21/_pdf


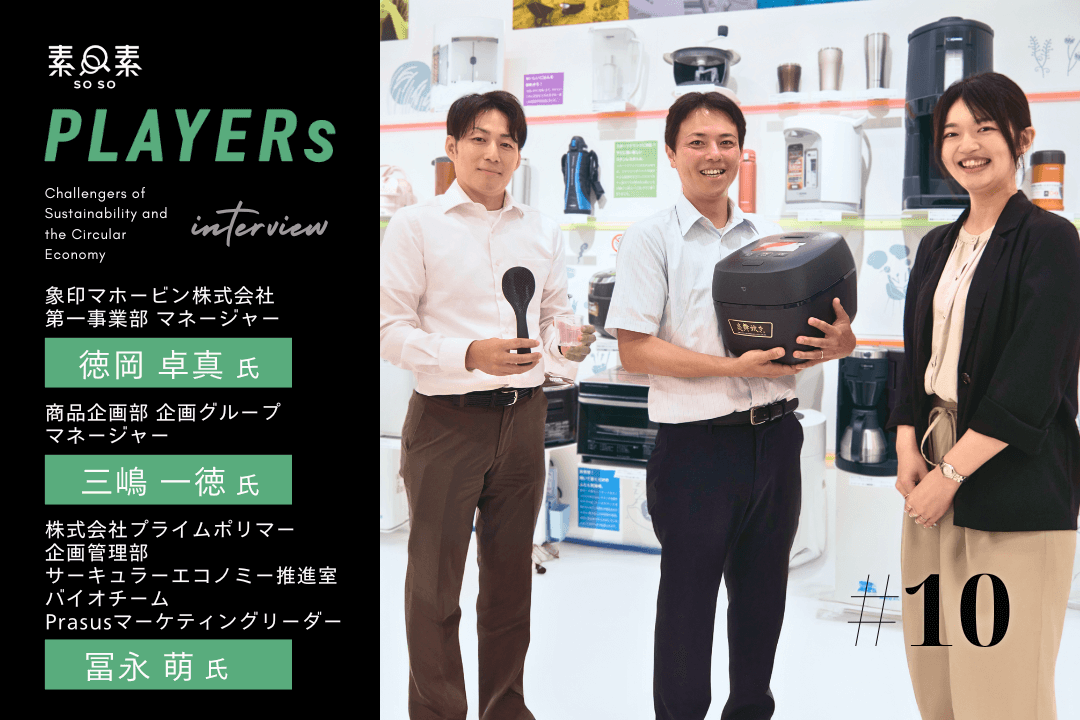
_%E5%BE%8C%E5%8D%8A.png)




_%E8%A8%98%E4%BA%8B%E7%94%A8(1080%20_720).png?width=220&name=PLAYERs%2313(%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E3%82%B7%E3%82%B0%E3%83%9E)_%E8%A8%98%E4%BA%8B%E7%94%A8(1080%20_720).png)






.png?width=600&name=%E3%83%97%E3%83%A9%E5%9B%B3%E9%91%91%E3%83%90%E3%83%8A%E3%83%BC_640260%20(002).png)