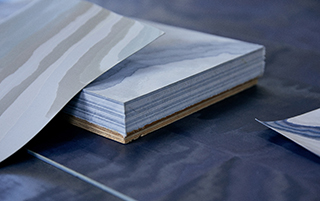「なんかいい」を形にする。理論を超えた吉泉流デザインの源流
MOLpチーム(以下、MOLp):東北ラボの空間に入った瞬間、家具にさまざまな素材が使われていて驚きました。それでいてどこか自然を感じられて心地いい。感性を刺激される空間ですね。
吉泉聡(以下、吉泉):ありがとうございます。ここは「天井のシミのように」というコンセプトで、幼いころに天井を見上げて木目の柄やシミを顔や雲に見立てていたように、想像を誘うような、予定調和から逸脱できるような、誰もが持っている創造性に働きかける空間にしたいと考えてつくりました。
 作品とインテリア、そして窓から見える仙台の景色が調和したTAKT PROJECT「東北ラボ」
作品とインテリア、そして窓から見える仙台の景色が調和したTAKT PROJECT「東北ラボ」
吉泉:そして、「あなたの暮らしを便利にします」というスタンスでデザインされたものとは対極にある、受け取った人から新しい考えが湧いてくるような「引き出すデザイン」のプロトタイプを生み出すための場所として、仙台に拠点を構えました。東京にもオフィスがありますが、そことは異なる機能を持っています。
 吉泉聡(よしいずみ さとし)
吉泉聡(よしいずみ さとし)
1981年、山形県生まれ。TAKT PROJECT株式会社代表。デザインオフィスnendo、ヤマハ株式会社デザイン研究所を経て2013年にTAKT PROJECTを共同設立。ロジカルな思考だけでは到達できない仮説を構想する「新しい知性」としてのデザインを志向し、実践している。2023年には21_21 DESIGN SIGHT企画展『Material, or 』展覧会のディレクターに就任した。
MOLp:吉泉さんはこの東北ラボで体現されているように、既存のデザインの枠組みを超える活動をされてきたイメージがあります。デザイナーになろうと考えたきっかけは何でしたか?
吉泉:きっかけは大学時代に遡ります。小さなころから、車や自転車、家電など、かっこいいものが好きだったんですよね。それで「ものづくりをするなら工学かな」と思って、大学は工学部に進みました。
工学というのはある種「数学的に、論理的にちゃんと説明できる」ことがすごく重要で、実験をして、定量化するというプロセスを積み上げてものをつくることがほとんどです。だけどそのアプローチだけでは、自分が求めていた「これ、かっこいいな」のような魅力をつくる部分にはなかなか辿り着けないと感じて。
そのとき、自分は「よくわからないけれど人間の心や体が動いてしまうもの」という、数字では表せない部分にも興味があると気づき、それらを包括できるのではないか? と考えデザインの道へ進むことにしました。
「どこまでが素材で、どこからがプロダクトか?」吉泉の代表作に共通する「面白さ」の理由
MOLp:吉泉さんは、現在に至るまで、さまざまなプロダクトデザインやインスタレーションを発表してきました。代表的な作品をいくつか教えていただけますか?
吉泉:『glow ⇄ grow』という作品でしょうか。この作品には、量産品の代表的な素材としてとらえられがちなプラスチックを使っています。プラスチックは型にはまった大量生産品のための素材というイメージがありますが、そうではなく、自然のなかで外乱を得ながら形づくられるプラスチックがあってもいいのではと考えて、「輝いて育つ」作品をつくりました。
近年の代表作といえるものは、そういったもともとの素材のあり方や与えられていた意味を剥がして、別の可能性を探った結果生まれたものが多いですね。
 吉泉が代表作と語る『glow ⇄ grow』。紫外線で硬化する光硬化性樹脂を垂らし、球体についているLEDや太陽の光で氷柱のように固めている。光の強弱によって硬化の度合いが変わるため、日が当たる窓側とその反対では形状が異なる
吉泉が代表作と語る『glow ⇄ grow』。紫外線で硬化する光硬化性樹脂を垂らし、球体についているLEDや太陽の光で氷柱のように固めている。光の強弱によって硬化の度合いが変わるため、日が当たる窓側とその反対では形状が異なる
MOLp:氷柱や鍾乳洞のように漸次的につくられる形なので、プラスチックのイメージがガラリと変わって、マテリアルの新しい側面に気づくことができますね。
吉泉:そもそもプラスチック製品を製造する過程では、日に当たると形状が変わってしまうといった「自然の外乱」は避けたいもの。それをあえてやることで、人間が制御する対象としてのプラスチックという、一般的な意味づけとはまったく違ったものになります。大量生産のためのプラスチックというのも、ひとつの在り方に過ぎないことに気づけるのではないか? ということです。
そして環境問題とプラスチックの関係は、大量生産・大量消費とプラスチックを結びつけた、人間側から見た素材への意味づけが根本的な問題だと考えるべきではないかと思うのです。
一方で『COMPOSITION』の場合は、電子部品と透明なアクリルを混ぜ合わせて固めた作品で、非接触の充電器から電気を通すことで光り、家電としても機能します。そこには、「どこまでが素材で、どこからがプロダクトか?」という境界線への問いが含まれています。
 電子部品を素材ととらえ、外装材である樹脂と混ぜ合わせて固めた作品『COMPOSITION』。複合材は電気が通る素材となっており、電子部品が実際に機能する状態で封入された照明。
電子部品を素材ととらえ、外装材である樹脂と混ぜ合わせて固めた作品『COMPOSITION』。複合材は電気が通る素材となっており、電子部品が実際に機能する状態で封入された照明。
吉泉:しかしこのコンセプトが最初からあったわけではありません。もともとは「アクリルっていろいろ封入できるけれど、LEDを封入したら美しいだろうな」という言語化できない衝動から生まれています。そうしてプロトタイプをつくるために手を動かしながら、「それはどういうことなんだろう?」と自分に問いかけて、逆再生するなかでコンセプトが見えてくることがあります。電子部品が装飾的な外装で覆われてしまう家電製品の在り方に、潜在的に疑問を持っていたのだと思います。
MOLp:そこが理系的な発想とは違うところですね。
吉泉:言語化できなくても「なんかいいな」と思うのは、おそらくなんらかの潜在的な理由があると思うんですよね。そして自分がいいと思うものはほかの人とも共有できるなにかがきっとあって、それを咀嚼していくことで何かが見つかっていく。逆に言葉から積み上げていったものって、どこか説明的で、あんまり面白くなかったり、響かなかったりすることが多々あると思うんです。
そして興味を起点に探究しながら形にしていったものは、最終的に言語化できる要素が必ずある。そして「なぜ面白いか」を突き詰めて言語化することで、みんなと共有することができ、アートではなくデザインにすることができるのだと思います。