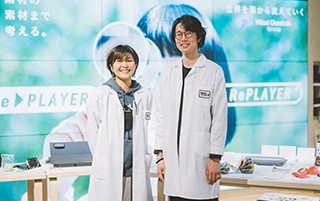アンリアレイジ・森永氏による講演会「トップデザイナーが考える素材の魅力」レポート
三井化学株式会社のオープンラボラトリー活動である「MOLp®」。今回は、素材から世界のファッションに革新をもたらしているトップデザイナーであるアンリアレイジ/森永さんをお招きし、「トップデザイナーが考える素材の魅力」をテーマに開催されたMaterial Nightの様子をレポートします。MTDO/田子さんを交えたクロストークも実現し、ファッション業界の第一線で活躍してきたデザイナーならではの視点で、素材のもつ可能性について語っていただきました。
「ANREALAGE(アンリアレイジ)」 代表・デザイナー 森永邦彦氏

早稲田大学卒業後、2003年、アンリアレイジ設立。
テクノロジーや新技術を積極的に用いた服は、毎年パリコレクションで発表し、世界的に注目を集めている。
【ANREALAGE・森永氏による講演】
「アンリアレイジ」は日常の中にあって、ふとしたときに出会う非現実的な捩れに目を向け、デザインの原点として表現するブランドで、テクノロジーを積極的に取り入れたデザインでも注目を集めています。デザイナーにして代表である森永氏からは、新たな知覚体験を与える新素材との出会いのエピソードが語られました。

森永:三井化学さんの素材とのつながりは「視覚」と「触覚」の2つのポイントがあったのですが。まずは触覚についてのお話からしたいと思います。
僕が服づくりの際に考えていることは、そのファッションで着る人に何かしら「それまでになかった知覚」をまとわせること、新しい体験をもたらしたいということです。

森永:アンリアレイジは2018年の夏に、ライゾマティクスの真鍋大度さんと石橋素さん、ダイアログ・イン・ザ・ダークの檜山晃さんと共に、これまでの知覚方法をアップデートする「新しい知覚」を探るプロジェクト「echo」を日本科学未来館で発表しました。
ファッションの世界は、視覚が何よりも重要視される分野ですが、視覚に頼らない人にとっても、ファッションが果たせる役割があるのではないか。着飾ること以外のファッションが持つ機能を拡張して、ファッションの壁を超えたいと思ったことがきっかけです。そこから、盲目の方が生きている特別な感覚世界を、服に落とし込むプロジェクトがはじまりました。彼らの知覚を補助する白杖という道具をヒントに、空間を知覚できる皮膚のような器官を服によって人に備えさせるウェアの開発を行いました。
コウモリは超音波を出して自分と周囲との距離を測ります。これを人間にも応用できないかと考えました。視覚に頼って生きていると、聴覚、触覚、嗅覚をあまり使わなくなりますが、目の見えない人は、私たち以上に、自分の発した音の反響を感じ取り、自分と周囲の建物や障害物との距離が知覚できます。
そこから発想を得て作ったのが「echo wear」。服には空間を知覚するセンサーがついていて、視覚が機能しない暗闇でも周囲の環境との距離を測れる服です。障害物が迫るとそのセンサーが反応し、振動することではじめて空間を認識できる仕組みです。

森永:先に述べた体験型展示「echo」では、来場者にこの服を着てもらい、アイマスクをつけた状態で空間を歩くという体験をしてもらいました。
衣服を皮膚感覚に近づけるためにecho wearは、三井化学さんの「アブソートマー®」。人の体温で軟質化する特殊な材料を使って形成しました。ハンガーにかけている状態では硬さのある生地ですが、体温によって生地はやわらかくなり、人体を包むようにフィットします。これによって自分の皮膚の延長のように感じることができるようになっています。これも新たな体験として、今日はぜひ実物を着てみてください。

森永:今回は周囲の環境に対するセンサリングでしたが、この精度を変えることでより遠くのもの、例えば夜空に浮かぶ星を知覚することも、目に見えないダニのような小さなものも知覚することが可能になります。そこから新たなコミュニケーションが生まれるのも楽しみですね。
「視覚」で楽しむ2019SSコレクション、テーマは「CLEAR」
センシング技術を取り入れて「触覚」に訴えるユニークな服づくりに取り組んだアンリアレイジ。続いては「視覚」をキーワードにしたパリコレクションのトピックへと移ります。
森永:僕の「ANREALAGE」というブランドは、「日常と非日常・リアルとアンリアル」というのをテーマに、その「日常」と「非日常」が合わさった瞬間にファンタジーが起こるのではないかという視点で服を作ってきました。
ブランド設立当時に取り組んでいたのはとにかく細かな仕事。一着にとても時間をかけて、1000ピースを超えるような生地を縫い合わせてパッチワークのジャケットを作ったりしていました。今日僕が着ているのも一見真っ黒のジャケットに見えますが、別々の生地を2000ピースほど接ぎ合わせたものなんです(笑)。

森永:今回のパリコレクションのテーマは「CLEAR」。透明なものと黒いものなど、対極にあるものをどう合わせるかを素材の観点から考えてきました。
例えば真っ白なドレスの色が変わる、光の部分と影の部分が反転する……といった仕掛けを考え、紫外線の波長に反応して色が変わる素材を糸として織り込んでいきました。

森永:パリコレでは、紫外線を当てて黒くした状態でランウェイに登場し、その色が徐々に薄くなっていき、ショーのフィナーレのタイミングで透明に戻るという構成にしました。
これに使用したのが、三井化学さんのMOLp®Caféで見た「不知火」に見られるような、フォトクロミック(調光)素材です。
素材をボタンのような形状や板状にしたり、フィルム状の薄さにしたり、さらに細く、糸のようにしたり……と、短い期間でしたが三井化学さんに多大な協力をいただいたおかげで、作品を発表することができました。

森永:余談ですが、日本とフランスでは紫外線量が異なります。日本では真っ黒だったけど、フランスでは紫がかった黒になるんですね。こうした絶対性のなさはとても面白いなと感じました。
デザイナー2名によるクロストーク。クリエイティブの源泉と、服づくりにおける素材との向き合い方とは?
森永氏による講演に続いては、MOLp®のクリエイティブパートナーである田子學氏をモデレーターに、業界の第一線で活躍する両氏によるクロストークを実施。
両氏のクリエイティブの源泉と、これからの服づくりや新素材への期待について聞きました。

田子:まずはお話、ありがとうございました。いろいろなことに挑戦されていますが、そのアイディアの源泉はどのようなところから得られているのでしょうか?
森永:僕は「絶体絶命!」という状況に追い込まれないと何かが出てこないタイプなんです。実は今日も、ここに持ってきている服を一度タクシーの中に忘れてきてしまって(笑)。そういった状況になると、必然的に「どうしようか」とすごく頭を使って考えますよね。そういったときに、今置かれている状況への解決策やアンサーが浮かびます。 服作りについては、「なんでも服にしちゃおう」という気持ちが常にあります。「これを服にしたらどうなるだろう?」って考えていて、想像していくととまりません。絶対服にならないでしょう、って思うようなものが多いですから。
田子:僕らはみなクリエイターということもあると思いますが、共通しているのが「どうやったらできるか」を常に考えていますよね。僕もそうです。そのためには当然「なぜ」という気持ちを常に持つようにしていますし、真実かのようなことを言われても「本当にそうなのかな?」と自分で問い直しています。それらを「そうなのか、当たり前なのか」と受け入れてしまったら終わりだと思っていて、もっといい生活とか、もっと豊かにとか、そういったことを考えていると、いろんなヒントが目に入りますよね。
異業種間のコラボレーションは、「お互いの専門分野に無知」だからこそ面白い

-素材メーカーとディスカッションする意味のようなものはありますか?
森永:今回一緒にものづくりをしたのですが、熱量や思考は僕らととても近いなと感じました。反対に違うなと感じたのは、流れている時間の速さ。僕たちは半年に1回発表をするので、そのためには普段皆さんが1年や2年かけてつくっているものを「1ヶ月で作ってほしい」とお願いすることもありました。僕はとてもしつこく「こうしたい」「もっとこうできないか」とお願いしてしまうのですが、それに全部応えてくださったことには感動しました。三井化学さんのような規模の大きな企業で、どんな球も返す、形にして成し遂げるってすごく難しいと思っていました。ですが実際に服として完成させることができた。これはすごいことだと感じましたね。
森永:きっと、ファッションという分野は三井化学さんにとってブルーオーシャンだったんだと思います。だからこそいろいろトライしてくださったのでしょうし、なまじファッションに慣れている会社だとこんな無謀なことはしてもらえなかったかも(笑)。今回の制作で実現できなかったこともたくさんあるので、それも叶えていきたいです。
「わからない」っていうのはある種いいことでもあると思っています。固定観念があると、できないと思ってしまうことが増える。異業種だからこそ「わからないけど、やってみよう」と思ってもらえることがある。お互いが「わからない」からこそトライできることも多いと思います。そういう関係のなかからイノベーションが起きたらいいなと思っています。
田子:ありがとうございました。

ファッションという分野から素材の新たな魅力を発見し、コレクションとして作り上げている森永氏。両氏の服づくりに対する思いや共通点、新たな素材を用いた服づくりへの期待感を感じられる、貴重な機会となりました。