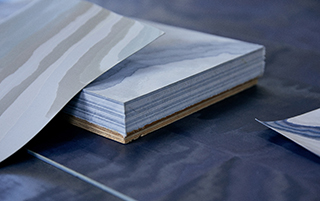outline
日々の生活や仕事のなかで「素材」と向き合う人たちの考え方に触れる、連載「そざいんたびゅー」。今回取材に訪れたのは京都。クラフトマンシップを持ちながら、3Dプリンターをはじめとするデジタルファブリケーションの技術を応用し、新しい設計や生産方法の開発に取り組んでいる設計者集団「新工芸舎」です。
日用品として長く使いたくなる工芸的な味わいをプラスチックから見出す新工芸舎の主宰・三田地博史さんは、「つくることは生きること」と語ります。こうしたものづくりの思想はどのようにして生まれたのでしょうか? ものづくりをとおして見出した素材の面白みや、かつての民藝運動にもつうじる「新工芸」の未来について、話を聞きました。
取材・執筆:宇治田エリ 写真:原祥子 編集:川谷恭平(CINRA)
「新工芸」はどうやって生まれた?企業に就職して経験したものづくりの葛藤
MOLpチーム(以下、MOLp):伝統工芸が盛んな京都の地で「新工芸」と銘打ち、デジタルファブリケーション技術を用いたものづくりを行っている三田地さん。どのような経緯で新工芸というコンセプトが生まれたのでしょうか?
三田地博史(以下、三田地):新工芸に取り組む新工芸舎自体は2020年に立ち上がりましたが、そのきっかけはぼくが学生だったころまでさかのぼります。
ぼくは平成元年生まれで、生まれたときから樹脂製品が身のまわりにあふれていました。樹脂は身近にあるはずなのに自分では工作できない、よくわらない存在でした。しかし、大学生になり、3Dプリンターに出会ったことで、樹脂という素材が手触り感を持って扱えるようになり、一気に身近に感じられるようになったんです。

三田地:大学ではプロダクトデザインを専攻していたため、最初の数年間はプロトタイピング(試作品をつくり事前検証をすること)の目的で3Dプリンターを大学に持ち込み使っていました。そこから徐々に、「3Dプリンターでどうにか商品に仕立てて販売することができれば、就職しなくてすむんじゃないか」と思うようになって。
3Dプリンターの製法と素材に適したかたちはなにか、試行錯誤するようになったんです。その手触り感のあるものづくりがとても楽しくて、学内でも「3Dプリンターの人」になっていましたね(笑)。
MOLp:なるほど。
三田地:でも、結局は企業に就職し、インハウスデザイナーとして2年半、巨大なシステムのなかでものづくりを展開するという経験をしました。そこでは社会の歯車の1つになってしまったような、すごく不自由な感覚を覚えて。経済的合理性に特化した環境では、ものづくりをするうえで大切な「喜び」が失われてしまうと強く感じましたね。
そこで退職を考えていたとき、新工芸舎の母体である「YOKOITO」のメンバーが新しい拠点をつくろうとしていて、声をかけてもらいジョインしました。あらためて考えると、3Dプリンターなどのデジタルファブリケーションを使ったものづくりも、自分が大切にする工芸的な思想が宿っていることに気づき、「新工芸」と名づけ、新工芸舎としての挑戦が始まったんです。
MOLp:YOKOITOという母体に対して、新工芸舎はどのような立ち位置なのでしょうか?
三田地:現時点では、YOKOITOという会社のクリエイティブ部門という立ち位置です。YOKOITOは3Dプリンターの販売などを行ない、「AM(Additive Manufacturing)」という積層造形法の推進を目指しています。
新工芸舎では、先ほどお話した新工芸をコンセプトに、デジタルとアナログの垣根を越えた新しいものづくりの在り方そのものを生み出そうというグループで、その立ち上げと主宰にぼくが関わっています。

京都から生まれる現代の「民芸運動」。ものづくりの喜びを最大限に
MOLp:今日は新工芸舎の拠点、旧下京図書館にお邪魔していますが、京都らしい味わいのある建物ですね。
三田地:この建物自体は戦前に建てられたもので、最初は地域の公民館として使われていました。建物の随所に意匠が見られ、階段には石の彫刻、ドアには地元の彫金職人による装飾などがあり、地域の方々が集まるサロンのような場所として使われていたそうです。
そのあと下京区の図書館になりましたが、図書館が移転したことで建物を誰も使わなくなったところ、われわれが入居しました。かなり古い建物だったこともあり、DIYで改装して。本当に大変でした(笑)。



MOLp:新工芸舎を代表するシリーズに、「編み重ね」という技法を用いた、素材を編んだような温かみのある質感が魅力の「tilde(チルダ)」があります。そちらも拠点立ち上げ後に誕生したのでしょうか?
 編むように樹脂を溶かして積み重ねた「tilde(チルダ)」
編むように樹脂を溶かして積み重ねた「tilde(チルダ)」

三田地:「tilde」のアイデアが生まれたのは、ぼくがインハウスデザイナーとして働いていたときで2016年ごろですね。当時、「FDM(Fused Deposition Modeling)」と呼ばれる熱溶解式3Dプリンターを使っていたのですが、それはフィラメントと呼ばれる細い糸状の樹脂を熱で溶かし、積層するという成形法なので、どうしても積層の跡として表面に縞が残ってしまい、量産された製品のクオリティーではないものに見えるんです。
当時のぼくはそれをどうにかしたいと考えて、模索していった結果、「そもそも繊維状に出力していくもので、金型に樹脂を流し込んで圧力で押しつける成形法とはまったく違うのだから、ふさわしいデザインも違うはずだ」と気づいたんです。そこで「あえて繊維っぽさを活かしたデザインにしよう」ということで、tildeシリーズの初期作品である「HyotanStand」の原型が生まれました。
当時からこのアイデアは面白いと感じていたため、新工芸舎を立ち上げて最初に取り組んだのも、このtildeシリーズでした。工芸家が窯で土を焼いてものづくりをしてきたのと同様に、ぼくたちは3Dプリンターを使って樹脂と1対1の関係で向き合っている。こうした姿勢が「新工芸」を象徴すると感じて展開していきました。
 FDMを使って制作する三田地さん
FDMを使って制作する三田地さん
MOLp:立ち上げから3年目となるいま、新工芸はどのような存在になりつつあると思いますか?
三田地:まだまだ浸透しているとはいえませんが、伝統工芸が盛んな京都では意外にも、そのコンセプトや表現が「面白い」と言われることが多く、ある程度受け入れられているように思います。
これまでの社会では、1人のデザイナーが1万人に対して物をつくる方が効率や品質が高く、良いとされてきました。しかしそれは、つくる喜びや発想する喜びが最小化されてしまうということでもある。それよりもこれからの時代は、100人の工芸家が100人に対して、アイデアを考え、手を動かし、かたちを与えていった物の方に価値が宿ると考えていて。
1926年(大正15年)に柳宗悦、河井寛次郎、浜田庄司らによって提唱された「民芸運動」のように、新工芸も時間をかけて多角的にアプローチすることで、日常的な暮らしのなかで使われてきた物や、そのものづくりのあり方、そして消費のあり方をとらえ直すきっかけを与えていけるのではないかと考えています。