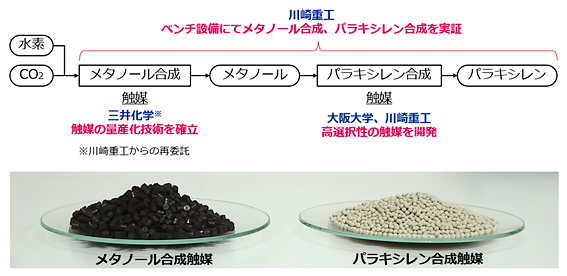当社グループは2050年カーボンニュートラルの実現に向けて、2030年度までに2013年度比でGHG排出量40%削減を目指すこととし、VISION 2030の非財務目標の一つに設定しています。これに向けて、京葉地区における出光興産(株)とのLLPにおけるナフサクラッカーの1基化、グリーンイノベーション基金※を活用した大阪工場ナフサクラッカーへのアンモニア燃焼分解炉設置、省エネおよび再エネ導入の推進などの検討を進め、2030年度GHG排出量の目標達成に目途を付けました。
今後も低炭素化、脱炭素施策を順次実行するとともに、2050年までについては、市場や顧客等の外部環境の整備・変化が前提となりますが、前述の施策に加えて新技術の開発や事業ポートフォリオ転換等による80%以上の削減を、残り20%についてはCCUS等のカーボンネガティブ技術の開発・導入などを進めていく考えです。
また、2019年度よりインターナルカーボンプライシング(ICP)を導入しています。投融資の判断材料にICPを考慮したIRR(c-IRR)を追加することにより、経済的な機会だけでなく将来の環境負荷増加リスクも考慮した投融資の必要性を討議しています。戦略を加速する施策の一つとして、2022年度にはインターナルカーボンプライスを3,000円/t-CO2eから15,000円/t-CO2eに見直しています。