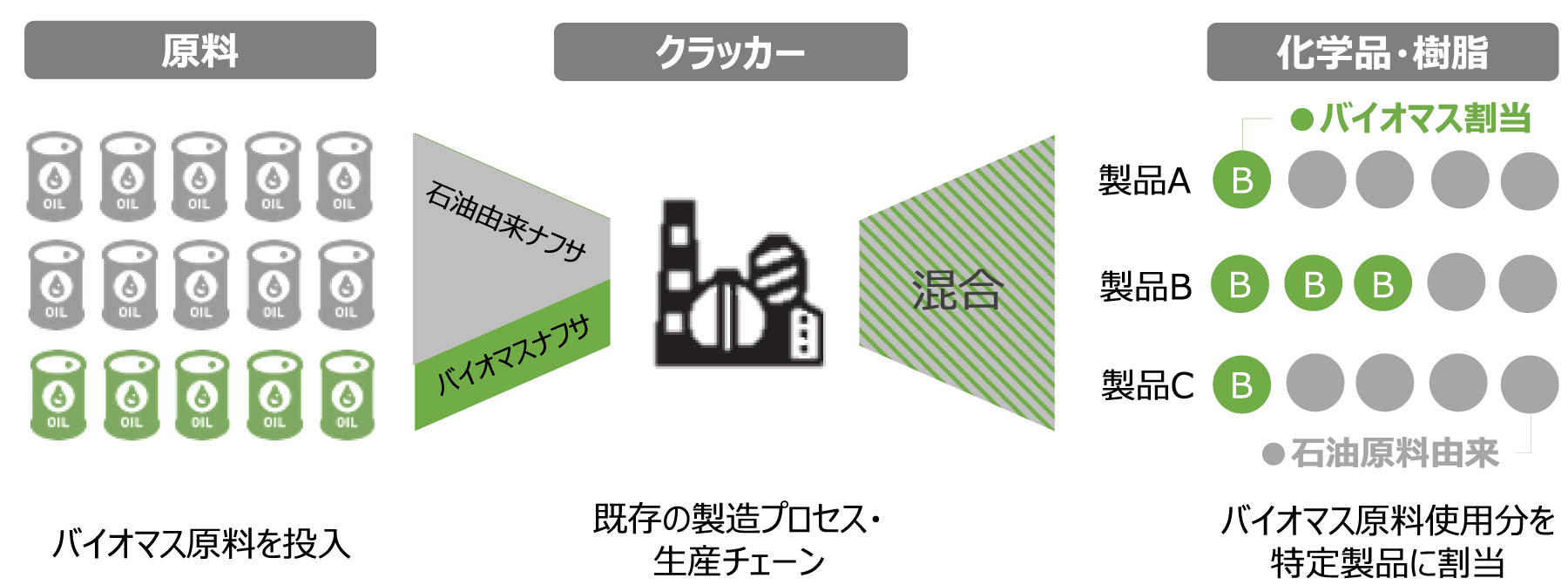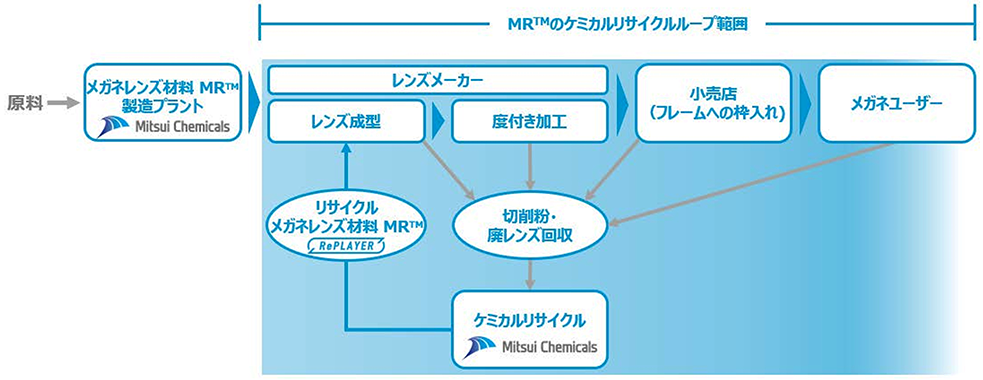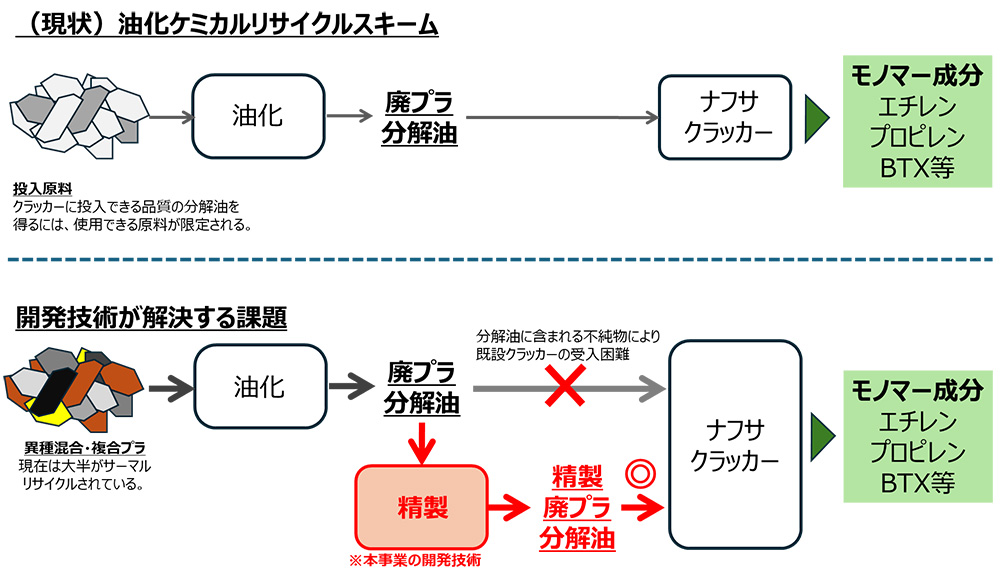資源の大量消費と廃棄を前提とした従来型のリニアな経済活動は、地球環境に大きな負荷をかけています。当社グループは、理念である「素材メーカーとして材料・物質の革新と創出」を通して、豊かで快適なくらしを100年以上にわたり支えてきました。そしてこれからも、環境と社会の持続可能性を高める「サーキュラーエコノミー」への対応強化を通じて社会課題解決に貢献します。
このような考えのもと、VISION 2030の基本戦略では全事業を対象としたサーキュラーエコノミー型ビジネスモデルの構築を掲げ、当社グループの主要製品であるプラスチックについてサプライチェーン全体を視野に入れ、バイオマス戦略、リサイクル戦略に注力しています。これら2つの戦略とプラスチックごみ問題への対応を通して資源循環を促進し、サーキュラーエコノミーの実現に貢献していきます。