三井化学グループは、「安全はすべてに優先する」という経営方針のもと、全グループを挙げて様々な安全活動に取り組んできました。しかしながら、2012年に岩国大竹工場でレゾルシン製造施設爆発火災事故が発生してしまいました。二度とこのような事故を起こさないよう抜本的安全対策をはじめとした再発防止に努めています。
安全・保安
重大事故防止
経営トップの安全・保安に対する強いコミットメント
三井化学社長は、「安全の日」、「全国安全週間」等にて、「安全はすべてに優先する」という経営方針を当社グループ全社員に繰り返し発信しています。また、生産・技術本部長をはじめとする当社幹部も、三井化学および国内外関係会社の生産拠点を訪問する等、現場の安全文化醸成に向けて積極的に関わっています。2024年度の実績は以下のとおりです。
- 新年挨拶会、期首講話で本社社員に安全最優先の直接訓示(国内拠点に同時中継)
- 安全の日に関連して、社長の安全訓話をグループ全体に発信(日本語、英語)
- 安全の日に工場で社員に直接訓示(国内生産拠点に事前撮影の録画配信)
- 全国安全週間に関連して、社長メッセージをグループ全体に発信(日本語、英語、中国語)
- 安全対話等を通じて工場の社員に安全に関して直接訓示
- 社内報の安全特集に、社員へのメッセージを掲載
安全の日
三井化学では、レゾルシン製造施設爆発火災事故を風化させないために、事故のあった4月22日を「安全の日」として制定しており、例年「安全を誓う式」や講演会を拠点ごとに開催しています。
2024年度は、各拠点に向けて、社長の安全訓話動画を配信しました。本社の式典には、専務執行役員(CTO)をはじめ、本社在勤の役員、部長が出席しました。また、社長が岩国大竹工場の式典に参加し、「安全はすべてに優先する」ことを全員で誓い合いました。
 岩国大竹工場「安全を誓う式」(2024年4月)
岩国大竹工場「安全を誓う式」(2024年4月)
抜本的安全対策の発展
三井化学は、2012年4月22日に発生した当社岩国大竹工場レゾルシン製造施設爆発火災事故を厳粛に受け止め、全社の安全・保安の確保に関わる問題点を徹底的に見直し改善する、抜本的安全対策への取り組みを開始し11年が経過しました。2022年度以降はこれまでに展開してきた抜本的安全対策を更に発展させ「新たな抜本的安全対策」として、「安全のあるべき姿」を実現し、無事故・無災害を追求するため、三井化学グループ全体で取り組んでいます。
新たな抜本的安全対策推進の全体像
新たな抜本的安全対策は、関係会社を含めた三井化学グループ一丸の体制で取り組んでいます。
※1 ステアリングコミッティ:
「抜本的安全」を速やかに進行させるために、図に示すメンバーが一同に会し、全体課題を議論し、活動の方向付けを行う場のこと。
※2 PL:
パートリーダー
新たな抜本的安全対策への取り組み
新たな抜本的安全対策の3つの課題と7つの方策を策定し、そこから各本社工場および各国内関係会社にて、具体的な方策に落とし込んでいます。2024年度も、従来からの本社経営層と工場の対話の他、教育や安全文化診断、高度なリスクアセスメント(RA)の展開、工場の働き方改革や若手育成、女性活躍推進、自律的キャリア施策の展開を継続するとともに、その範囲を関係会社に広げ、グループ全体への展開を図っています。
新たな抜本的安全対策の「課題と方策」
| 課題1:ライン管理者が、世代交代と働き方改革に対応したマネジメントができること | |
|---|---|
| 方策①:工場内の業務負荷軽減 | |
| 方策②:ライン管理者のマネジメント力の更なる強化 | |
| 課題2:技術力のさらなる向上と、技術伝承を確実に行なえること | |
| 方策③:技術評価システムの運用強化とリスクアセスメントの高度化 | |
| 課題3:安全最優先の徹底とプロ意識の醸成、業務達成感が得られること | |
| 方策④:「安全はすべてに優先する」の徹底 | |
| 方策⑤:自主・自律(自分事)によるプロ意識の醸成と強化 | |
| 方策⑥:チーム力、職場内コミュニケーション、組織間連携の強化 | |
| 方策⑦:若手およびライン管理者のキャリア・アッププランの充実 | |
VISION 2030達成に向けた取り組み
当社グループは、VISION 2030の非財務目標として「重大事故・重大労災件数ゼロ」を掲げています。この目標の実現に向けて、「異常現象・事故※1 5件以下」「重視する労働災害度数率※2 0.15以下」という数値目標を設置し、これら目標の達成に向け3つの重点課題を特定しています。各課題に対する方策は、毎年度の行動計画に具体的な年度目標として落とし込み、体系的に取り組みを進めています。
※1 異常現象・事故:
爆発、火災、漏えい、破裂、破損、異常反応の事象のうち、関係法令で異常現象または事故として扱われた事象。ただし、フロン漏えいや微量漏えいを除く。
※2 重視する労働災害度数率:
休業労働災害に限らず、不休業または微傷災害であっても、その原因が重篤と判断されるものを「重視する労働災害」と定義し、100万延実労働時間当たりの発生件数(度数率)としてモニタリングしている。
高度なリスクアセスメント体制の構築
三井化学では、設備の新設・増設・改造時に加えスタートアップ・シャットダウン、緊急時等の非定常操作においても危険源摘出、リスク評価およびリスク低減を実施してきました。更に高度なリスクアセスメント(RA)体制構築のため、「網羅的な視点での危険源発掘」、「評価者でバラツキの無いリスク評価」、「確実なリスク低減」に取り組んでいます。「網羅的な視点での危険源発掘」では、RA実施者の力量バラツキを解消するため、職場のRAを推進するRAリーダーを育成し、力量認定後に配置しています。「評価者でバラツキの無いリスク評価」では、定量的リスク評価法(HAZOP-LOPA※)を導入しています。「確実なリスク低減」では、工場横断的に助言、指導するRAアドバイザーにより、第三者視点でのRA結果の妥当性確認を行っています。これらの活動は2020年度に大阪工場へ先行導入後、市原工場、岩国大竹工場へ順次展開し、2023年度より本体全工場での運用を開始しました。また、全社横断的に推進・支援するRAスペシャリストを本社に配置しています。
当社は、引き続き高度なリスクアセスメント体制の構築を推進し、自主保安力を強化していきます。
※ HAZOP-LOPA:
Hazard and Operability Studies-Layer of Protection Analysis。
正常からのずれを網羅的に想定し解析するHAZOPで摘出されたずれの「原因」、起こりうる「影響」に対して、「原因」の発生確率と既存の安全対策が突破される確率の積から「影響」(火災、爆発等)の発生頻度[ /y]を求め、追加のリスク低減措置を決定する手法。
スマート工場を目指して(先進技術を活用した安全・保安)
三井化学グループは、先進的な技術を効果的に導入することにより、高効率で安全・安定な次世代工場(スマート工場)を目指しています。
導入している主な技術
| 主な目的 | 具体的な技術 |
|---|---|
| 設備異常・漏洩の早期検知、故障予測 | 無線振動センサー、ガス漏洩検知カメラ、異常予兆検知システム、回転機電流兆候診断、ワイヤレス超音波板厚計測システム 等 |
| 安全性向上 | 労働災害危険源抽出AI、作業リスク検出技術、制御系サイバーセキュリティーシステム 等 |
| 現場作業支援、業務効率化 | ウェアラブルカメラ、現場作業支援モバイル端末 等 |
| 運転の効率化 | AIによる自動・最適化運転技術 |
今後も日々進化し続ける先進技術の導入を通じて、運転と保全を変革し、生産技術力を強化することにより、さらなる安全・安定運転に貢献していきます。この一環として、化学プラントの複雑な現象に対するデータ解析や、プラントの状態を予測するモデル構築などが出来る生産技術系データサイエンティスト育成にも取り組んでいます。
安全文化診断
三井化学グループは「安全を作れる文化の醸成」に向けて、新潟大学と連携して安全文化診断を実施しています。この安全文化診断を通じて、職場の強み・弱みの見える化が可能です。また、階層別のあらゆるギャップについて職場内討議を重ねることで、職場のコミュニケーション向上ツールとしても活用しています。
各工場が3~4年に1回の頻度で診断を行っています。1回目の診断によって見えてきた弱点に対し、安全教育や小集団活動への積極的参加、業務負荷の削減、技術伝承等の改善策を講じることにより、2回目の診断でその成果を確認しています。
2024年度に診断を受けたある関係会社では、前回の受診結果にて「相互理解」と「学習伝承」の軸に弱みがあると判断され、ライン長との対話や座談会などの推進と、一般社員向けのWeb教育の導入などの対策を実施してきた結果、今回の受診結果でそれぞれの軸の改善が確認されています。
※ 安全文化の8軸モデル:
「動機付け(モチベーション)」、「組織統率(ガバナンス)」、「積極関与(コミットメント)」、「相互理解(コミュニケーション)」、「資源管理(リソースマネジメント)」、「作業管理(ワークマネジメント)」、「学習伝承(ラーニング)」、「危険認識(アウェアネス)」の8つの軸をもとに安全文化を評価。この安全文化の8軸モデルに基づいた、110問の設問への回答により、工場・職場の状況が見える化され、同時に業界のベンチマークと比較した強み・弱みがわかる。
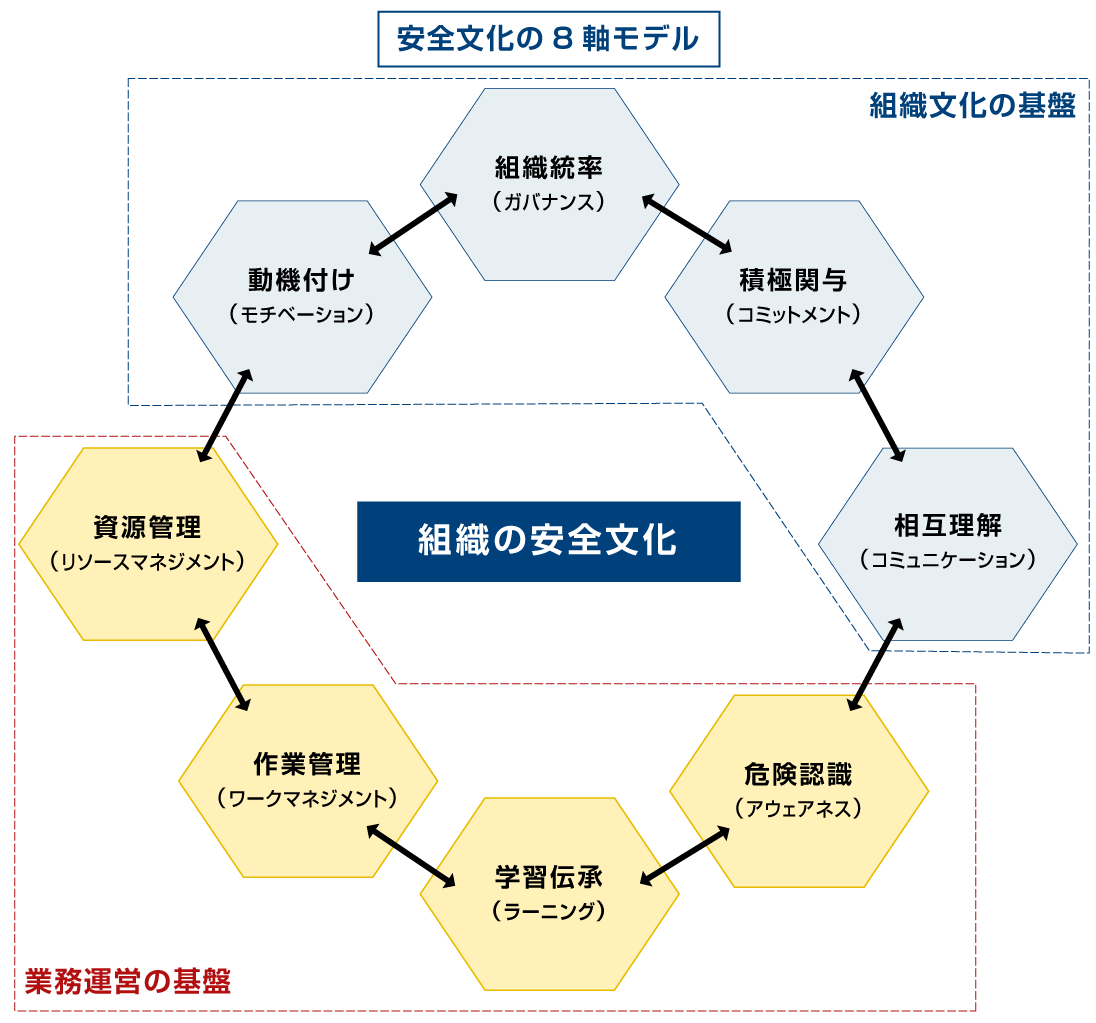
安全文化診断の展開状況(~2024年度までの受診実績)
| 三井化学※ | 1分工場が2回目、5工場が3回目、1分工場が4回目を受診済み。 VISION HUB® SODEGAURAが受診済み。 |
|---|---|
| 国内関係会社 | 対象17社中、13社(22工場)が受診済み。 内、4社(8工場)は、2回目を受診済み、 4社(5工場)は、3回目を受診済み。 |
| 海外関係会社 | 対象26社中、4社(4工場)が受診済み。 内、1社(1工場)は、2回目を受診済み。 |
※ 三井化学の工場長がレスポンシブル・ケア運営の責任を持つ工場構内関係会社を含む。
保安力の第三者評価受診
三井化学グループは、安全文化診断の自己点検に加えて、第三者評価として保安力向上センターによる保安力評価を継続的に受診しています。これは、主に石油・石油化学品を取り扱う製造業を対象に、安全基盤と安全文化の観点から保安力を評価するもので、保安力に関する強みや弱みが数値で見える化できます。保安力向上センターは、保安力評価を通じて、日本の化学産業の安全レベルの引き上げを目指しており、当社はその趣旨に賛同しています。
2018年度までに、大阪工場、市原工場、岩国大竹工場が1回目の評価を受診し、2023年度に岩国大竹工場、2024年度に大阪工場が2回目の評価を受診しました。安全基盤および安全文化に関するこれまでの評価は、全般的に「良好なレベル」との判定を得ていますが、評価結果として確認された課題についてさらなる改善に取り組んでいます。特に、「安全設計基本方針」について種々の基準に散在した状態で分かりにくいとの指摘を受け、本社主導で上位規則となる「保安管理細則」を制定し、2024年度は工場への展開に取り組みました。
 保安力評価の様子(岩国大竹工場)
保安力評価の様子(岩国大竹工場)
高圧ガススーパー認定事業所の認定取得
自律型高度保安の取り組みが評価され、2021年に三井化学大阪工場、2022年に市原工場、2024年に岩国大竹工場が、経済産業省が制定する特定認定事業者制度※における特定認定事業者(通称:スーパー認定事業所)に認定されました。この認定制度では、先進技術の導入やリスクアセスメント、従業員等への教育・訓練について従来の認定制度に比べて高レベルな取り組みを求められており、それらの取り組みの継続的改善により自主保安力を強化するものです。
今後もグループ全体として自主保安力の強化・改善に努めます。
※ 特定認定事業者制度:
経済産業省が2017年4月より開始した制度であり、特に高度な保安の取り組みを行っている事業所を「スーパー認定事業所」として認定し、認定を受けた事業者は、自主保安における設備の検査方法、点検周期などの自由度が高まるものです。それにより国際的な競争力の強化にもつながります。
