人材マネジメント
従業員エンゲージメント
エンゲージメントサーベイへの取り組み
当社実績、傾向
VISION 2030の達成には従業員一人ひとりのエンゲージメントの向上が必要と考え、三井化学グループ全従業員を対象としたグローバル従業員エンゲージメント調査を2018年から開始しました。現在はエンゲージメントスコアをグループの非財務目標にも設定し、社内外にも開示をすることで、継続的なモニタリングと改善アクションを行っています。また2023年度からは、モニタリングの頻度を上げ、目標に向け、よりタイムリーに取り組みを推進するべく、従来3年に1回程度の頻度であった調査を毎年実施することとしました。
2024年度エンゲージメント調査については、グループ従業員の90%から回答を受け、スコアは36%と前回と同水準でした。要因別に見ると、強みを持つ領域、課題のある領域、ともに前回から大きな変化はないものの、全体的にスコアの改善傾向がみられ、前回の調査結果を踏まえたアクションが一定の成果を上げていることがうかがえます。
※ エンゲージメントスコア:
エンゲージメント関連質問6問の平均が4.5以上の高い肯定度合い示す社員の割合(4:どちらかと言えばそう思う、5:そう思う、6:強くそう思う)を表しており、スコアの改善を図るだけでなく、強いエンゲージメント意識を備える従業員が増えることも目的として、取り組みを進めている。
エンゲージメントスコア推移と目標値
エンゲージメント要因スコア(強みを持つ領域・課題のある領域)
| 課題のある領域 | 強みを持つ領域 | |
|---|---|---|
| 2024年度 | 総報酬と認知 25% | 法令・社則遵守 69% |
チームワーク 23% | 安全 56% | |
人材活用と配置 22% | 雇用主としてのブランド 43% | |
| 2023年度 | 総報酬と認知 | 法令・社則遵守 |
チームワーク 22% | 安全 | |
| 人材活用と配置 21% | 雇用主としてのブランド 42% |
各組織におけるポストサーベイアクション
サーベイを実施するだけでなく、調査から見えてきた課題に対する打ち手を、人事部門が経営層とも連携して行うグループ全社の取り組みに加え、「ポストサーベイアクション」として各関係会社や三井化学本体の部レベル組織それぞれの取り組みとしても実行しています。調査結果から見られる各組織の課題にきめ細かくタイムリーに対応するだけでなく、「各組織がなぜそのような課題に直面しているのか」といった本質的な課題にも目を配りながら、各組織のリーダーが率先してエンゲージメントスコア向上に取り組んでいます。
ポストサーベイアクションの代表例として挙げられるのは、①職場内コミュニケーションの強化(交流イベント、勉強会の実施等)、②表彰制度の活用、③キャリアや日常業務に関する1on1面談などです。社員同士の結束を強めることを目的としたものから、将来のビジョンを明確にし、意欲的に業務を遂行するための施策まで、職場ごとに様々なアクションを検討・実行しています。
これらのポストサーベイアクションは、三井化学本体部レベル組織の他、関係会社合わせて182の組織で策定・実行されておりその立案・実行率は100%であり、当社グループ一体となった取り組みとして具体的な施策は社内ポータルで共有され、他の組織からも参照することができます。
評価・報酬
適正な評価に沿った処遇は、社員のモチベーションを高め、優秀な人材の獲得・育成・リテンション、そして三井化学グループの発展に大きく関連する重要な制度であると考えています。
業績評価・報酬の基本的な考え方
三井化学では、予め設定した職務目標の達成度と行動に基づいて業績評価を行い、その結果を報酬に反映しています。
職務目標の設定は、経営ビジョンに基づく経営計画を各部門の方針・目標に落とし込み、そこから導き出された重点課題を各グループやチームの目標として整理。最終的には、各個人の担当職務の目標に反映させることで、個人の目標達成がチーム、グループ、部門、ひいては全社の目標達成につながる仕組みとしています。報酬面においても、部門の目標達成度が個人の賞与に連動する仕組みとしています。また、10月頃に中間確認を行い、内外環境の変化に応じて目標を柔軟に見直せる制度として運用しています。
業績評価にあたっては、評価結果のフィードバック面談を通じて、上司が職務目標の達成度評価および行動評価の結果を、理由とともに丁寧に伝えます。個々人の特性を踏まえた上で、長所や改善点を共有し、必要に応じた支援を行うことで、従業員の育成につなげています。特に行動評価については、「グローバル・コアコンピテンシー評価」を導入しており、行動指針およびコア・バリューに沿った行動をとっているかを、具体的な事実に基づいて本人が振り返り、上司が評価・フィードバックを行います。これにより、行動指針およびコア・バリューの浸透・定着を図っています。
目標設定から評価までのプロセスでは、期初の目標設定時、期中の中間確認、評価・フィードバックの3回の面談を基本とし、上司と部下が対話を重ねます。これらの機会に加え、日常的かつ定期的なコミュニケーションも推奨しており、当社の経営計画の実現と社員一人ひとりの納得感につながる制度運用を目指しています。
これらのプロセスは、グループ・グローバルで導入しているタレントマネジメントシステム(Workday)により一元管理されており、環境変化や人事異動等に伴う目標の見直しにもタイムリーに対応可能です。達成状況も随時アップデートできるため、上司・部下双方が常に参照できる環境を整えることで、効果的な対話の機会を創出しています。
なお、三井化学労働組合では、組合員のフィードバック面談の実施率や納得度を調査しており、その結果は労使で共有し、評価制度の適正な運営に活かしています。
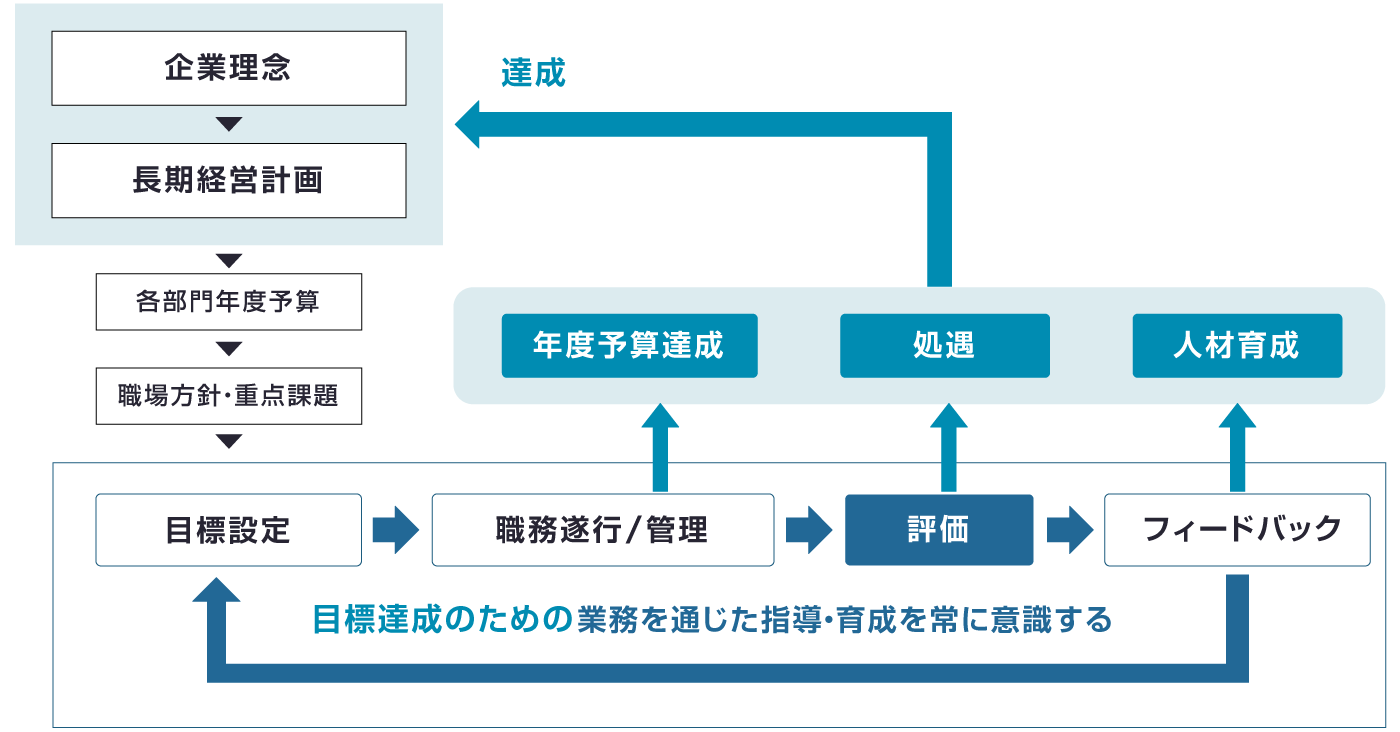
VISION 2030に連動した人事制度改定
VISON 2030の実現に向け、従業員のエンゲージメント向上や成長・積極的なチャレンジをさらに促すべく、2022年4月に人事制度を改定しました。改定にあたっては、エンゲージメント調査結果を活用し、目標設定や評価など個人業績管理の仕組みの改定と、評価の透明性・具体性の向上を図りました。
具体的には目標設定において、VISION 2030よりバックキャストした変革目標を役員および部長が率先して設定し、協働を目的に部下へ公開することを定めました。また、失敗を恐れず、一段高い目標に対して粘り強く挑戦することを促すため、達成時は加点評価としました。変革目標は上位職者から段階的に導入し、今後、対象者を課長以下に広げていく計画です。
また、評価について、これまで評価区分ごとに一律だった賞与額の配分を、それぞれのパフォーマンスに応じてきめ細かく調整できる仕組みとし、個々の貢献により直接報いる内容としています。賞与は、個人業績に加えて連結コア営業利益額に連動して支給額を決める算定方法としていますが、VISION 2030の業績目標を目指す上で、さらなる動機づけとなるよう、高い営業利益の際にはさらに支給額が増える制度に見直しています。
また、行動評価のベースとしてきたグローバル・コンピテンシーの見直しも行いました。VISION 2030実現に向けて必要な要素と議論されてきた「チャレンジ促進」、「実行力強化」、「コミットメント強化」、「社内外連携の促進」を反映しています。さらに、従来行動評価軸のひとつにあげていた「多様性(Diversity)の理解」に、公平(Equity)、包摂(Inclusion)の視点を加えた内容に改定しました。イノベーションを創出しVISION 2030の実現を目指す上で、単に「多様性」を理解するだけでなく、公平に発言や行動の機会を提供すること、個性豊かな他者を活かすことで、新たな発想や成果に結びつけることを促すことが目的です。また、職務グレードごとに求められる具体的な行動やレベルを、新たに「リーダーシップコンピテンシー」として定義し、評価することで、VISION 2030の実現に向けた行動を促進しています。
法定賃金の遵守、魅力的かつ競争力のある報酬水準の設定
三井化学グループは、事業のグローバル化が進展する中、従業員の報酬について、各国・地域の法律を遵守し、法定の最低賃金支給、所定労働時間または法定労働時間を超えた労働に対する代休付与または割増賃金支給などを行っています。その上で、各国・地域の労働市場において、魅力的かつ競争力のある報酬水準・体系になるよう整備しています。報酬水準は、人材獲得競争下、市場における当社業績のポジショニングに応じた設定とすることを基本的な考え方としており、行政機関等による各種賃金統計や外部調査機関の報酬データベース等を活用し、定期的に見直しています。
この考え方に基づき、2022年度以降、毎年ベースアップを継続しており、競争力のある報酬水準の確保に努めています。特に2025年度には、新卒採用における競争力の確保を目的として、初任給の大幅な引き上げを実施しました。
また、制度の運用にあたっては、年齢・年功要素を極力排除し業績成果を反映した公平公正な運用を行い、これら給与・賞与および評価・昇給などの体系を社則やハンドブックなどで従業員に公開しています。
また、人権ワーキンググループの重要な検討テーマの一つとして、ディーセント・ワーク(働きがいのある人間らしい仕事)を実現する上で重要な、生活賃金(従業員とその家族のために適切な生活水準を維持するのに十分な報酬が支払われているか)を取り上げています。
中長期的な取り組みへの表彰
年度の目標に対する貢献は、業績評価により報酬に反映しておりますが、中長期的な取り組みにも報いるべく、「全社表彰制度」を運用しています。本制度では経営目標の達成と企業体質の変革に向けた社員の活性化を目的とし、主に中期および長期経営計画に基づく戦略課題の方策立案及びそれと同等レベルの活動について、3年間の取り組みを表彰対象としています。また、審査の基準としては、成果のみならずGHG排出量削減など当社のサステナビリティの目標として掲げているテーマへの貢献度も評価指標として取り入れています。
グループ・グローバルでの評価と報酬の明確化
三井化学グループは国を超えてグループ横断的に優秀な人材の獲得・育成・リテンションをしていくにあたり、「グループ・グローバル評価ガイドライン」と「ポジションマネジメントに関するグローバル・ポリシー」を展開し、グループ内で共通化した評価指標の広範かつ公正な適用とポジションの可視化、報酬プロセスの明確化を進めています。
グループ・グローバル評価ガイドライン
評価の仕組みや考え方、設計等を整理した「グループ・グローバル評価ガイドライン」を2016年に策定し、全グループ会社に配布しました。本ガイドラインはMBO(目標管理)とグローバル・コアコンピテンシーの二軸で構成されており、これに基づいて地域統括会社(米州、欧州、アジア太平洋、中国の四地域をそれぞれ統括)の人事部門が、域内企業の評価制度構築・変更・運用を支援しています。
とりわけグローバル・コアコンピテンシーは、当社グループの人材開発における共通指標として採用しており、各層ライン長のリーダーシップ開発研修にともない実施する「360度フィードバック評価」も本コンピテンシーに基づいています。
グローバルポジションマネジメント
当社は2004年以降、管理社員を対象に職務記述書を策定し、各ポジションの職務の大きさに応じ処遇する職務評価制度を導入しています。一方で、グローバルでの拡大にともない、長期経営計画と整合した組織および職務を適切にグループ全体で設計していく必要があるため、2020年度に「ポジションマネジメントに関するグローバル・ポリシー」を当社グループに展開しました。現在、当社グループには約18,000のポジションが存在し、そのうち海外ベースのポジション割合は約40%となっています。それら国内外のポジションについて、当該ポリシーによりグループ内におけるポジションの新設や廃止に関する基本的な理念や仕組み、決裁権限およびプロセスを明確にしました。この展開にともない、新たにグローバルグレードも導入し、標準化された職務評価基準に基づいたグループ内ポジションの可視化を進めています。
関係会社役員任免・報酬ポリシー
2021年度に、三井化学グループ会社の役員人事ガバナンスに関するグローバル・ポリシーを展開しました。本ポリシーにて、120を超える国内外連結対象関係会社における、①役員の任免、②報酬水準・構成の考え方、③報酬の決定プロセスを明確化しています。当社グループは、本グループ共通のポリシーに基づき、任免プロセスの透明化、およびグループ全体の業績と連動した適切な報酬の決定を実現し、グループ全体で一体的な役員報酬マネジメントを実行していきます。
生産的な職場環境の整備
「三井化学グループの持続的成長」と「従業員の幸福と自己実現」を同時に、かつ高いレベルで実現することを目指した「三井化学グループ人材マネジメント方針」に基づき、働きやすい職場環境の整備と成果の最大化を目指しています。
働き方改革
三井化学では、これまで、超勤時間の削減、効率的な働き方を実現する就業制度の充実等、主にインプット(労働投入)の効率化に主眼を置いた「働き方改革フェーズⅠ」を着実に進めてきました。
一方で、世の中の変化が激しく、将来の予測が困難な、いわゆるVUCA※の時代においては、個々の社員の自主・自律、組織としての協働が今まで以上に必要となります。
そこで近年は、多様な働き方を志向し、従業員エンゲージメント向上、成果値の最大化を目指す「働き方改革フェーズⅡ」に力を入れて取り組んでいます。
※ VUCA:
Volatility(変動性)、Uncertainty(不確実性)、Complexity(複雑性)、Ambiguity(曖昧性)の頭文字を取り、先行きが不透明で、将来の予測が困難な状態を表す
テレワーク制度
当社は2019年4月にテレワーク制度を導入しましたが、テレワーク可能日数は限定的であり、利用者も少数でした。しかし、2020年の新型コロナウイルス感染拡大以降、感染予防といった安全の観点から緊急対策としてテレワーク可能な日数の上限を時限的に廃止する措置をとり、利用者が急拡大しました。その結果、ITツールの拡充やITリテラシーの蓄積等が進み、テレワーク時に行える業務が拡大し、感染症予防といった安全衛生面だけでなく、働きやすさや成果の最大化につながる新しい働き方の点でもテレワークが浸透しました。このような状況をふまえ、2021年7月1日付で、テレワーク制度の規定を改定し、月4日以上の出社を条件にテレワーク可能な日数を大幅に広げました。本改定により、以前よりも出勤とテレワークの組合せの自由度が大きく高まったことを受け、社員・組織の成果を最大化すべく、自らの働き方をより主体的に考えるきっかけとなるよう働きかけています。
副業従事要領制定
当社は、2021年1月に「副業従事要領」を制定し、会社への届出・許可に基づき、管理社員が副業を実施できる仕組みを整備しました。その後、2022年1月から一般社員にもトライアルとして同じ要領を適用し、運用上の課題等の検証を経た上で、2024年1月に「副業従事細則」を制定し、副業制度を正式に導入しました。2025年3月までの間に、110名の社員が当社業務と両立して副業に従事しています。従事業務の内容は、本人の専門性(経験、知見、資格など)を活かしたコンサルタント、技術指導、教育機関での講師、翻訳などです。従事者は、社外の経験を通じて視野を拡げるとともに、副業を通じて得た知見を活かし、当社業務においても積極的に貢献しています。
副業を通じ期待する効果
社外の経験
視野・知見の拡大
当社業務への貢献
服装自由化
当社は、2020年8月、出社、テレワークなど働く場所に限らず、勤務中の服装要領を明確化すること、また、ダイバーシティの観点から性別による禁止事項を設けず、共通の規定を設けること等を目的として、「本社・支店勤務者の服装要領」を改定しました。本改定では、安全性、作業性・清潔を保つこと、TPOを意識し、特に顧客や社外取引先との面会時には、社会慣行を尊重することを念頭に、社員が自ら考えて適切と判断する服装を着用することとしています。本要領により、社員の選択肢を増やす中、変化を許容し、自ら考え行動する文化のさらなる醸成を目指しています。
社内公募制度
三井化学では、従業員一人ひとりが主体的にキャリアを考え、自ら選択していけるよう、会社として多様なキャリアの選択肢を提供することを目的に、2004年より社内公募を導入しています。現在は主に新規事業や成長領域での業務拡大に関連したポジションを対象に、年4回、各部門のニーズに基づいて募集を行っています。2024年度は、のべ90件の公募案件に対して38名の応募がありました。また、募集に当たっては、募集部門による説明会を開催し、業務内容や求められるスキル、得られる経験などを応募者に正確に伝えることで、マッチングの向上にも努めています。その結果、2024年度は12名が実際の異動に結びつき、自身のキャリア希望に沿ったポジションで新たな業務に就いています。
超過勤務削減、有給休暇の取得率向上のための取り組み
三井化学は、各月における時間外および休日労働時間の合計が80時間以上となる社員をゼロにすることを目指した活動を進めています。取り組みとして、超過対象者が発生した場合は、上司へ原因と対策についてヒアリングを行い、再発防止策を全社で共有しているほか、超勤削減のためのスキル研修を毎年継続して実施しています。一般社員向けには「タイムマネジメント研修」を実施し、仕事上の習慣の見直しやスケジューリング、メール処理の具体的な方策を指導しています。管理社員向けには「組織運営ワークショップ研修」を実施し、効率的な組織運営の具体的な方策の習得と残業削減のための計画策定を指導しています。
また、通常、化学プラントは長期連続運転を行っていますが、生産への影響を最小化するとともに設備の安全を十分に確保するため、一定の限られた期間に一斉に停止して補修や点検を行う定修と呼ばれる作業を行う必要があります。この定修による特定時期への業務集中を避けるため、作業の見直し、OBや契約社員を含めた人員の強化などに取り組んでいます。
適切な労働時間管理
三井化学では、36協定で定めた時間外・休日労働時間の上限を遵守し、実績に応じた手当の支給を行うとともに、適切な労働時間管理に取り組んでいます。毎月、従業員の時間外・休日労働時間の見える化を目的として、部署ごとおよび個人ごとの実績を管理者に共有しています。管理者は、他部署との比較や、自部署内で特定の個人に業務が集中していないかを確認し、働きやすい環境の整備に活用しています。また、月間の超過勤務時間が80時間を超える従業員が発生した場合には、人事部門が対象者の管理者にヒアリングを実施し、一人ひとりの社員について原因の究明と改善に向けた具体的な対策を検討・実行しています。
有給休暇の取得率向上
三井化学は、社員の健康維持や心身のリフレッシュを目的として、年次有給休暇の取得率向上に取り組んでいます。休暇取得の促進のため以下の施策を実施しており、2020年度に70%だった全社平均の取得率は、4年間で8ポイント向上し、現在は約8割に達しています。
- 長期休暇、連続休暇の計画的取得推奨
- 休日に挟まれた出勤日等を有給休暇取得サポート日に設定し、休暇の取得を推奨
- 職場別有給休暇取得率の集計と通知・指導
- 特定個人への業務集中の見直し
- 職場内のスケジュール共有化
フレキシブル・多様な働き方を促進する仕組み
ワーク・ライフ・バランスを考慮した施策
三井化学は、育児や介護といったライフイベントに対応する休暇や休業、勤務時間、収入面の配慮について法定以上の制度を整備し、その周知を図ってきました。
テレワークやフレックスタイムなど柔軟な働き方を支援する制度をはじめ、失効した年次有給休暇(特別休暇)を入院だけでなく通院などの治療でも取得できるように制度の改定を行い、治療と就労の両立をより強力にサポートしています。制度、施策の一覧はこちらをご覧ください。
主な制度・施策(三井化学)
| 年次有給休暇 | 年間20日、半日単位で取得できる。(入社1年目は入社時期に応じ、最大20日) |
|---|---|
| リフレッシュ休暇 | 有給。年間、連続する2日取得できる。 |
| 特別休暇 | 有給。失効した年次有給休暇を積み立てて(上限60日)、傷病・介護・育児・社会活動の事由で3日以上勤務できない場合に取得できる。病気治療や不妊治療には半日単位で取得可能。 |
| フレックスタイム制度 | コアタイムなし。労働時間を1日単位ではなく、1ヵ月単位で管理する。 |
| テレワーク制度 | 育児、介護などの事由を問わず、月4日以上の出社を要件として利用できる。 |
| 副業の解禁 | 副業を実施したい社員が、会社の了解を得て副業に取り組めるよう、副業を認める条件、副業時の取り扱いを整備。トライアル期間を経て、2024年1月に制度化。 |
| 社会活動休暇 | 有給。年間2日まで取得できる。 |
| 配偶者海外転勤時休職 | 3年を限度に休職することができる。 |
| 育児休業 | 最長で4年間取得可能。最初の5日間有給※1とし、男性社員の取得を奨励している。 |
| 短時間勤務措置(育児) | 小学校6年生までの子どもの育児のために1日3時間を限度に取得できる。 |
| 会社託児所の設置 | 市原工場・VISION HUB® SODEGAURAの近隣に2009年開設。 |
| 看護等休暇 | 有給。親族※2に看護等が必要なとき、年間20日まで取得できる。 |
| 介護休業 | 要介護状態または要支援状態にある親族※2の介護のために、対象親族1名につき1年まで取得できる。 |
| 介護休暇 | 有給。要介護状態または要支援状態である親族※2の介護のために年間20日まで取得できる。 |
| 短時間勤務措置(介護) | 親族※2の介護のために1日3時間を限度に取得可能。同一事由について1年まで。 |
※1 以降の休業期間については、最長2歳になるまで、三井化学共済会、雇用保険より賃金の約60~70%が給付
※2 配偶者、父母、子、祖父母、配偶者の父母・祖父母、兄弟姉妹・孫・配偶者の兄弟姉妹
その他の制度の利用状況についてはこちらをご覧ください。
育児休業からの職場復帰支援プログラム
当社は、子育て中の社員が出産・育児休業からスムーズに職場に復帰し、高いモチベーションを保ちながら働ける環境を整えるべく、「職場復帰支援プログラム」を制度化しています。このプログラムでは、産前休業前、育児休業中、復職後の各段階に応じた支援内容を明確にし、社員と上司の双方が安心して復職準備を進められるようサポートしています。
休業前には、本人と上司による面談を行い、業務の引き継ぎ、休業中の連絡手段、各種手続き等について確認します。復職前にも、上司との面談を実施し、復職後の働き方のイメージ、職場の受入れ体制や担当業務について共有し、相互に理解を深めます。復職後には、各種制度の手続き等に関する説明や支援を行い、円滑な職場復帰を支援しています。
また、復職後の両立期においては、ワーク・ライフ・バランスに悩む社員(男女問わず)に向けて、両立している先輩社員との対話等を通して、両立術や多様なキャリア形成の仕方を学び、自身のキャリアについて考える研修機会の提供も行っています。
育児休業取得率(三井化学籍社員)
男性の育児参画推進
当社は男性の育児参画を推進しており、育児休業の最初の5日間を有給とすることで男性社員の取得を促しています。男性の育児休業については配偶者の妊娠を人事部に申請してもらい、人事部から上司宛に対象男性社員との面談を依頼し、上司が育児休業の取得の意思の確認、制度の説明をします。育児休業の取得やその期間について迷っている男性社員には、人事部の担当者が面談し取得時期や取得可能な回数など育児休業の取り方の工夫を伝えたり、上司との間に入り調整をしたりすることで取得を促しています。
また、育児に関する社内制度やその具体的な活用方法などを掲載したガイドブックやマニュアルを作成し、妊娠が分かってから育休を取得するまでのフローを分かりやすく解説するとともに、気になる育休中の収入に関する情報なども掲載しています。さらに、経営陣からのメッセージや、育児中の男性社員やその上司のインタビュー記事を掲載し、男性も積極的に育児に関わることを推奨しています。
2023~2024年度にかけては、全ライン長を対象にした男性育休研修を実施し、研修前は男性育休を理解する受講者は38%でしたが、研修後には86%に改善するなど、マインド変革も進んできています。また、パパ社員だけではなくママ社員も配偶者と共に参加できる父親学級も開催し、男性育休を取る事の重要性を当事者にも理解してもらうような取り組みも進めています。2024年度には、社長が「男性育休取得率100%」を宣言し、取得率向上に向けた取り組みを加速しつつ、さらには取得日数にも目を向け、脱「取るだけ育休」も進めているところです。

介護と仕事の両立
当社では、介護をしながら働く社員のサポートを行っています。介護をする社員の離職を防ぐため、「公的制度や社内制度を使って介護をマネジメントする」という考え方を周知する目的で、毎年、介護と仕事の両立をテーマにしたオンラインセミナーを開催しています。しかし、いつ来るかわからない介護は当事者意識がわきにくいため、セミナーへの参加者が限定される傾向にあります。
そこで、2021年度からアウトリーチ策として社内ポータル掲示板に介護に役立つ情報を四半期毎に投稿しています。投稿には社内外情報へのリンクを貼り付け、必要な詳細情報に簡単にアクセスできるよう工夫しています。また、バックナンバーをポータルにまとめて掲載し、急な介護が始まった社員に必要な情報を素早く伝えることにも役立っています。これまでに取り扱ったテーマは「介護休暇と介護休業の違い」「介護保険認定制度」「認知症介護」「親子のコミュニケーション」「専門職との連携」などです。テーマに関係する信頼できる外部のYouTube動画を紹介し、介護に必要な知識を深められるようにしています。一方で、人事部だけでは解決しきれないような介護に関する悩み相談も増えてきており、2024年度は外部の専門家による介護相談窓口を設置し、より複雑化する介護と仕事の両立の悩みに対してサポートできる体制を強化しています。
育児・介護休業者の評価取り扱い
三井化学は、賃金・賞与・退職金の金額決定および昇格において、育児・介護休業者が不利にならない評価としています。育児・介護事由の休業者は、当年度の出勤率が一定基準以上の場合、出勤していた期間の目標達成度・行動に基づき、1年分を評価します。一定基準の出勤率に満たない場合、報酬決定や昇格が不利にならないよう無評価(No Rating)扱いとしています。
率直な対話と相互理解に基づく労使関係
三井化学は、労働協約において「企業グループ理念の実現」と「社員の幸福と自己実現」をともに達成することを労使共通の目標と定め、建設的かつ安定した労使関係の構築に努めています。経営課題の共有と意見交換、生産性向上、従業員のワーク・ライフ・バランスの向上といったテーマについて、労使間で率直な議論を行う場を重ね、社員一人ひとりが生きがい・働きがいを持つための基盤づくりを推進しています。なお、転居・転勤をともなう異動にあたっては、原則として1ヵ月前までに本人に通知を行うルールを採用しています。
労働組合
当社はユニオンショップ制を採用しているため、労使で合意した労働協約において「労働組合への加入が認められている従業員」は全員労働組合に加入しています。当社労働組合はすべての一般社員を代表しており、労使間の交渉結果はすべての一般社員に無条件に適用されます。一方、管理社員などマネジメントレベル以上の社員は労使合意により加入が認められていません。
海外拠点においては、それぞれの労働関連法制と従業員の自由な意思に基づき労働組合を結成できるよう運営しており、これを制限する行為は一切行っていません。
また、適正な労働条件の確保、人材開発、安全・環境、労働衛生・健康増進および品質管理の向上、差別やハラスメントを含めた懲戒等の重要事項については、労働協約にて定め、労使で確認をするとともに、組合員の労働条件等に関わる具体的施策については原則として労使協議を通じて決定しています。
さらに、労使経営懇談会や経営概況の説明等、労使間のコミュニケーションの機会も定期的に設けており、相互理解と信頼関係の構築に努めています。
定例的な労使のコミュニケーション
- 経営に関する懇談会
- 個別テーマ毎の懇談会
- 事業所労使懇談会
- 労使協議会
- 労使交渉
- 事業所労使協議会
- 事業所労使交渉
- 労使合同による調査・研究等の会合
主な労使協議テーマ(2024年度)
- 賃金改定
- 定年再雇用制度改定
- 時間外・休日労働時間および年次有給休暇取得状況
- 海外制度改定
- 懲戒規定改定
- 人事関連諸規則改定
