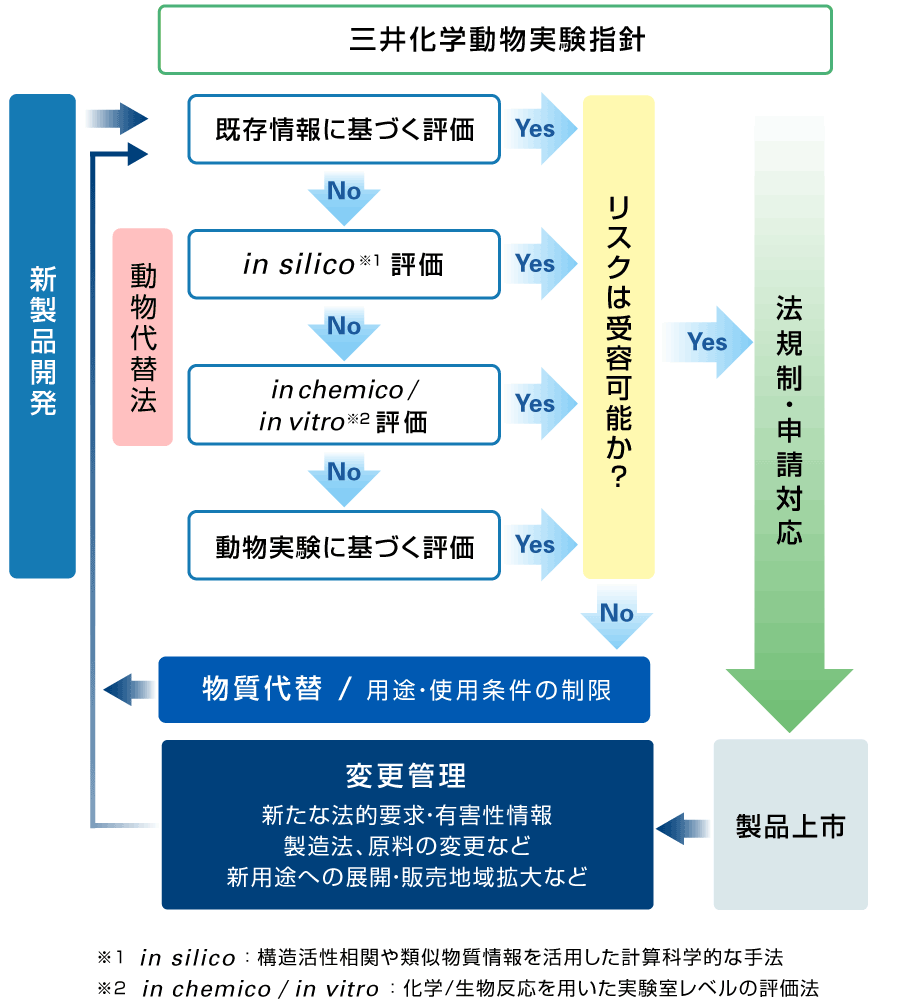人の健康および環境の保護と持続可能な開発のために、ライフサイクルを考慮した化学物質と廃棄物の健全な管理(Sound Chemicals and Waste Management)が提唱され、ICCA(国際化学工業協会協議会)でも展開されています。また、2030年に向けた国際的な化学物質管理のための枠組み(GFC: Global Framework on Chemicals)では、産業界を含むマルチステークホルダーによる自主的な化学物質管理の推進が求められています。
三井化学グループは持続可能な発展を目指すサプライチェーンの一員として、この健全かつ自主的な化学品管理の視点を取り込んだ事業展開と製品開発を進めています。